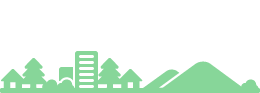老爺心お節介情報 第57号
能登半島地震による氷見市の被災状況と支援
4月4日~5日、能登半島地震の災害に遭った富山県氷見市へ、遅れ馳せながら富山県氷見市と氷見市社会福祉協議会へお見舞いに行けた。高齢の私が行っても何もできず、かえって足手まといになるだけだと訪問を控えていたが、漸くお見舞いに行けた。
氷見市は、能登半島の付け根に位置している。石川県の被災状況はテレビ等で報道されるが、氷見市も能登半島の一部をしめており、被災状況は厳しいもので、テレビなどの放映で感じたものとは、また違う状況だった。
いまだ、石川県奥能登地域には行けていないが、今回の地殻変動、激しい液状化による被害を見て、災害支援の難しさを改めて考えさせられた。
氷見市の林市長、森市民部長、高木氷見市社会福祉協議会会長、七分氷見市社会福祉協議会常務理事にお会いし、お見舞いを申し上げるとともに、宮城県石巻市での東日本大震災被災者へのソーシャルワーク支援をまとめた『東日本大震災被災者への10年間のソーシャルワーク支援』の本を贈呈してきた。
氷見市は市全体の高齢化率は40%であるが、被災状況が激しかった氷見市旧市街の北大町地区と石川県七尾市との県境にある姿地区はより高齢化が高く、生活再建が非常に厳しいものと思われ、物理的復興だけでは被災者支援はできず、生活全般の支援が必要で、そのためにはソーシャルワーク支援が必要であることをお願いしてきた。
被災状況は、氷見市社会福祉協議会の森脇次長、山崎次長、開上さんに案内とともに被災者支援の状況を聞かせて頂いた。お忙しい中対応して頂き、この紙上で改めてお礼申し上げたい。
氷見市の災害被災状況と被災者支援の状況は、氷見市社会福祉協議会が『氷見市の被災状況と災害ボランティア・支えあいセンターの現状』に詳しいので、ホームページなどを見て頂きたい。
Ⅰ、氷見市の被災状況の概況
氷見市は、現在の人口は約4万3千人で、世帯数1万4500世帯、高齢化率約40%で、市内に21地区社会福祉協議会が組織されており、約900人の生活のしづらさを抱えている人たちを支援する地域ケアネット事業(富山県単独事業)が展開されている。
2024年1月1日、午後4時10分に発生した能登半島地震により、200棟の家屋が全壊、400棟の家屋が半壊し、り災証明を受けた世帯は7000世帯という被害状況であった。断水も約1万4千世帯で発生し、全域復旧は1月21日までかかった。
人命の被害はなかったものの、液状化による被害は酷いものであった。建物の外観はそれほどではなくても、屋内が液状化の影響で住むことが難しいとか、道路のマンホールが隆起して、自動車の通行を妨げているとか、庭にある灯篭(氷見市には各家庭に石灯篭が沢山ある)が崩れたたり、台座がしっかりしている大きな墓石のある墓地が液状化で波打ってしまっているとか、その被害状況は家屋だけではなく、生活全般に大きく影響する被害が出ている。
被害が大きかった地区は、上庄川の北側の北大町地区と県境の姿地区に集中しているようであるが、上庄川の流域もそれなりに災害が発生している。上庄川の南側の南大町地区はあまり被害を受けていない状況とか、昔、布施の湖と呼ばれた湿地帯のあった地域ではあまり被害が発生していない(液状化が起きるのではと素人的には考えていた)状況をみて、地震のメカニズムが良く理解できない。
Ⅱ、被災支援の取り組みで学ぶべき点
氷見市での被災者支援の状況を行政や医療機関等も含めて広く検証しているわけではないが、氷見市社会福祉協議会の活動から学ぶべき点を箇条書きにして、広く関係者の情報共有をしたい。
① 氷見市社会福祉協議会は「災害ボランティアセンター」という名称ではなく、「災害ボランティア・支えあいセンター」という名称で、1月3日に立ち上げている。
その際、共同募金会からの支援金を想定して、「kintone」のアプリを導入している。
しかしながら、氷見市の「災害ボランティア・支えあいセンター」は、ボランティアのニーズ・シーズのマッチングを行う需要供給の調整だけを行うのではなく、住民からボランティアの派遣要請があった際に、その要請を受け止めた上で、それ以外の生活支援の必要性があるかどうかを、申請のあった世帯に社会福祉協議会の災害時支援現地班の職員を派遣し、ニーズキャッチとともにアセスメントを行い、それをケア会議に掛けて、どういうボランティアを派遣するのかを決定し、派遣している。
私は、従来から、土砂撤去などのボランティアの派遣調整だけではないと言ってきたが、氷見市社会福祉協議会は「災害ボランティア・支えあいセンター」という名称に見られるように、生活全般に亘ってのニーズ把握と支援を考えている。これは大変素晴らしい考え方である。
実際のボランティア派遣申請の相談内容と派遣は、大きく3つに類型できる。
第一の類型は、
従来の土砂の撤去、家具の片づけ等のボランティアの派遣である。
第二の類型は、
専門技術ボランティアで、家屋内の応急修理や灯篭の撤去である。石材業者に依頼すると小さな灯篭の撤去で5~6万円、大きなものでは8~10万円掛かるところをボランティアにより、計200基の崩壊した灯篭の片づけが行われた。大きいものでは、灯篭の笠の部分だけで700キロもあるものをボランティアが片付けてくれたという。そのボランティアの人は、長野県の音楽家で、トラック、重機をレンタルリースして、持ち込み、一か月逗留してボランティア活動をしてくれたとのこと、私には想像もできない活動で、その人の思い、気持ち、活動費の捻出等後学のためにもいろいろと聞きたいと思った。
第三の類型は、
専門職による支援である。り災証明の手続きをするのに、多くの高齢者は写真も取れず、申請手続きに難渋していた。その際、お手伝いしてくれたボランティアは富山県の司法書士会の方々で、り災証明の手続きサポートをしてくれた。
氷見市社会福祉協議会の実践が素晴らしいなと改めて実感できたことは、富山県が単独で展開しているケアネット事業があるが、そのケアネットを構築されていた住民が900世帯あったという。そのケアネット事業の方々は、何らかの生活のしづらさを抱えており、日常的に見守りや声掛け、簡単な生活支援を地域の方々の力でおこなわれ、生活のしづらさを解決しているわけだが、そのケアネット事業の対象の方からは災害発生後「災害ボランティア・支えあいセンター」への相談・依頼が一件もなかったという。それはたぶん、地域の方々が日常の延長で対応してくれたのではないかと氷見市社会福祉協議会が説明していたが、これはすごいことで、普段の実践の成果と言わざるを得なく、私は感動した。
「災害ボランティア・支えあいセンター」への相談者の属性は、一人暮らし高齢者が23%前後、高齢者のみ世帯が18%前後、障害の方がいる世帯が4~6%前後という状況で、2週間単位で、大体300件~500件の相談申請の状況であった。
「災害ボランティア・支えあいセンター」は、旧体育館に開設されていたが、そのセンターに氷見市の拡大した地図が張ってあり、その地図上に、どこの地区で、どのような属性を有した人からの申請があり、どのような支援をしたかを色分けしたシールでマッピングしてあり、氷見市内の被害状況の分布とボランティアの派遣要請の状況が分るようになっており、緊急事態の状況にも関わらず、全体像を可視化している点も高く評価できる。
私は社会福祉協議会が運営する「災害ボランティアセンター」の使命は土砂の撤去、がれきの撤去ではないと言い続けてきたが、氷見市社会福祉協議会の「災害ボランティア・支えあいセンター」はまさに私の考え方を実践してくれた取り組みで高く評価したい。
氷見市社会福祉協議会の森脇俊二事務局次長の、"「災害ボランティアセンター」は支援に駆けつけるボランティアのためにあるのではなく、被災した住民を支援するためのものである。だから「災害ボランティア・支えあいセンター」なのだ"という発言は、とても印象的で、私は"我が意を得たり"と納得した。
氷見市の「災害ボランティア・支えあいセンター」の活動実績として注目しておく点は、
ⅰ)ボランティアの派遣依頼者からのクレームがゼロであったこと、ⅱ)ボランティア活動のリピーター率が高く、約70%にのぼる、ⅲ)日常的に災害協定並びに姉妹社会福祉協議会関係にある全国の社会福祉協議会(愛知県半田市、三重県伊賀市、長野県茅野市、宮崎県都城市、香川県琴平町の各社会福祉協議会)から職員が派遣され、富山県内社会福祉協議会からの支援も含めて一日11人の社会福祉協議会の職員が応援に入ってくれた点などである。
② クラウドファンディングによる支援金の造成
東日本大震災以降、被災者支援、被災地支援は必ずしも日本赤十字社、共同募金会、NHK等の従来型の募金団体への寄付とは異なり、クラウドファンディングによる特定の地域、特定のテーマ・課題に寄付する活動が増えてきた。
氷見市の「災害ボランティア・支えあいセンター」の運営費のみならず、氷見市社会福祉協議会は、経営している自前の建物や行政から指定管理を受けている建物でも大きな損害を発生している。このような状況の中で、募金活動はとても重要で、受動的にではなく、積極的に募金活動を展開する必要がある。
氷見市社会福祉協議会は、三重県伊賀市社会福祉協議会の協力・支援をもらい、1月12日からクラウドファンディングによる支援金の受付を開始した(締め切り2月15日)。
クラウドファンディングによる支援金の受付以前にも社会福祉協議会は1月5日より緊急支援募金を始めており、海外からの申し込みもあり、受付方法についての英訳ページを開設したりしていたが、より募金がしやすいように、クラウドファンディングによる支援金の募集を行った。
募金額の総額は、氷見市社会福祉協議会へ直接募金をされた募金が総計279件、1520万円、クラウドファンディングによる募金が164人で220万5000円、この他市役所やボランティアセンターなどに設置した募金箱に40万円余の募金があり、現時点では総計約1700万円余の募金となっている。
この他にも、共同募金会から災害支援助成ということで300万円の助成を得ている。
私は、大和証券福祉財団やSOMPO福祉財団などの助成団体へも申請をしたらと提言してきた。
③ 生活全般における伴走的ソーシャルワーク支援の必要性
氷見市では、行政の健康課を中心に、富山県保健師会の協力を得て、被害の大きかった姿地区、北大町地区などの1406世帯の生活支援の必要性に関するローラー作戦が行われた。このような調査は、宮城県石巻市でも医療・保健関係者により行われた。住民のニーズキャッチとしてはとても重要な取り組みであるが、石巻市でもそうであったが、どうしても医療面、健康面での聞き取りが中心にならざるを得ない。
私は、『東日本大震災被災者への10年間のソーシャルワーク支援』の本の中で書いた「社会生活モデル」に基づくアセスメントが被災者支援には必要であることを林市長たちに話をしてきた。
とりあえず、り災証明の交付を受けた約7000世帯を対象に、アンケート調査を行い、そこからスクリーニングして個別訪問調査による支援を展開できないか、その調査を行政、社会福祉協議会、外部の専門職、福祉系大学等の協働で行うことが必要ではないかと提案してきた。
このような支援のシステムとそこで使われるアセスメントシートの様式を確立しておく必要がある。そうでないと、これからの災害支援が毎回"賽の河原の石積み"のように、蓄積されず、結果として支援の遅れをもたらすのではないかと危惧している。
(2024年4月8日記)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。
阪野貢先生のブログには、「大橋謙策の福祉教育」というコーナーがあり、その「アーカイブ(1)・著書」の中に、阪野貢先生が編集された「大橋謙策の電子書籍」があります。
ご参照ください。
第1巻「四国お遍路紀行・熊野古道紀行―歩き来て自然と居きる意味を知るー」
第2巻「老爺心お節介情報―お変わりなくお過ごしでしょうかー」
第3巻「地域福祉と福祉教育―鼎談と講演―」
第4巻「異端から正統へ・50年の闘いー「バッテリー型研究」方法の体系化―」
第5巻「研修・講演録」
第6巻「経歴と研究業績」