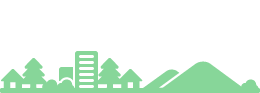老爺心お節介情報 第60号
酷暑の夏、皆様には如何お過ごしでしょうか。
私の方は、この暑さでは散歩もままならず、睡眠も熟睡できずと、少々へたり込んでいます。皆様には、くれぐれもご自愛の上、ご活躍下さい。
1.「災害と福祉」のテーマに、日本地域福祉学会はどう立ち向かうのか?
2024年6月15日~16日に、第38回日本地域福祉学会東京大会が文京学院大学・本郷キャンパスを会場にして行われました。昨年の長野大会に続いての対面・集合型の大会で、久し振りに旧知の方々とお会いでき、旧交を温めることができ、嬉しい、楽しい機会でした。
私は、大会課題シンポジュウム「災害と地域福祉」のコメンテーターとして参加をしました。
コメンテーターとしては異色かもしれませんが、この機会に社会福祉関係者に災害支援のあり方を考え直してほしいと思い、以下のようなレジュメを用意して臨みました。
学会としては、災害にどう対応したのかという状況報告はそれなりに重要ですが、それはある意味"善意"のレベルであり、学会としては、被災者支援にどう対応するのか、対応の際の視点は、方法はどうあるべきか、その視点、方法は他の分野の被災者支援の方々とどこが同質で、どこが異質なのかを整理・対応することが、"誠意"ある対応ではないのかという考えのもとに、コメントというより、学会への問題提起という意味合いでレジュメを作成しました。
日本地域福祉学会・文京学院大学大会
「災害と地域福祉〜ステージ毎の災害時支援と平時の人材育成を含めた災害支援を考える」
日本地域福祉学会名誉会員 大橋謙策
I、災害対策基本法、災害救助法等における救命•救急と災害福祉支援の区別化の必要性(研究仮説と分析視角①)
災害被災者支援にあったては、被災者の属性を4区分して、その階層ごとの属性に見合った支援が必要ではないかと提起した。
災害被災者の4階層化とは、第4層の人は、被災し、避難所生活を余儀なくされるが、生活に必要な基本的ライフラインが復旧すれば、自宅で生活が可能になり、かつ生活の復元力(リジリエント)を有している方々である。第3層の人は、被災前は自立した生活を送っていたが、被災により住宅再建、生活再建が難しくなり生活支援が必要な人、あるいは被災前は自立生活をしていたが、被災により心身機能に障害が生じ、何らかの支援が必要となった方々である。第2層の人は、被災前から要支援状況に置かれていたが、福祉サービスを利用できれば在宅での生活が可能だった人。第1層の人は、被災前から要支援状況で、かつ在宅生活が困難で、社会福祉施設などに入所していた人である。
- 2008年厚生労働省は、阪神淡路大震災、新潟中越地震の教訓を踏まえて「福祉避難所」の設置の必要性を認め、「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を発表した。そこで想定されている避難者は、介護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の在宅の要援護者である。
- このような被災者を区分化するということは、一般避難所に避難されてきた住民の方々を区分属性に応じてスクリーニングを行い、必要な支援を適切に行うという考え方にもつながる。このスクリーニングは、DMATの医学モデルに基づくスクリーニングとは違い、「社会生活モデル」に基づくアセスメントによって行われるべきものである。
- 第1層の人は、被災前から病院への入院、介護施設等への入所をしている方々であり、その利用している施設なり病院が被災した場合の、病院、施設の事業継続計画(BCP)が災害等のリスクマネジメントを踏まえて策定されている必要があるし、万が一それら病院、施設が被災によりサービスを継続的に提供できない場合の広域的支援、代替機能の確保が考えられていなければならない。DWATはこれらの課題に対応できるように広域、都道府県域、市町村圏域における「災害福祉支援ネットワーク」として構築が考えられた。
更には、在宅福祉サービスを利用しながら地域生活をしている高齢者や障害者に対しても、それら在宅福祉サービスを提供しているサービス事業者のBCPの在り方が、病院、施設と同じように考えられておかなければならない。
II、被災後の生活変容ステージ毎に変容する生活課題、生活のしづらさへのソーシャルワーク支援(研究仮説と分析の視角②)
被災者支援というと、イメージされるのが発災直後の支援である。しかしながら、災害被災者の生活再建の歩みは長い年月を必要としており、かつその必要としている支援の内容は、被災後の生活環境ごとのステージを考えて行われなければならない。それは、少なくとも緊急期、応急期、復旧期、復興期に区分できる。なおかつ、この区分は相対的な区分であり、その区分は画一でなく、個々の被災者の生活環境の変容とは必ずしも合致しないことを十分踏まえておくことが重要である。
III、被災による生活変容の課題とソーシャルワーク機能(研究仮説と分析視角③)
被災者支援は、被災者の生活再建に向けた経済的支援や住宅等の居住環境整備の支援だけでは対応できない。
被災者支援の課題を列挙するならば以下の様な課題がある。
- 親愛な方を亡くされた人へのグリーフケアの必要性とソーシャルワーク機能
- 失職及び将来の雇用不安とソーシャルワーク機能
- 貯蓄、金融資産等の経済力が脆弱な人への支援とソーシャルワーク機能
- 生きる意欲、生きる希望、社会的有用感を脆弱化させた人へのソーシャルワーク機能
- 生活技術能力、家政管理能力が脆弱な人へのソーシャルワーク機能
- 各種書類の整理、行政等への手続き能力が脆弱な人へのソーシャルワーク機能
- 社会関係、人間関係の持ち方が不器用な人へのソーシャルワーク機能
- 住居地が変遷することに伴うソーシャルサポートネットワークが脆弱化している人へのソーシャルワーク機能
- 被災以前には顕在化していなかった家族関係が、被災により家族形態が変容することによる支援が必要になった家族へのソーシャルワーク機能
- 仮設住宅、復興住宅の新しい生活様式、新しい家具、調理器の利用に馴染めない人へのソーシャルワーク支援
- 復興住宅での生活において緊急支援措置期間終了後の生活設計ができない人へのソーシャルワーク機能
- 障害をもち、その生活のしづらさが被災により、より深刻化している人へのソーシャルワーク機能
- 生活のリズムの変容、生活のリズムを作る日課の喪失、「ハレとケ」に関するアセスメントとソーシャルワーク機能
- 居住場所が変遷することに伴うソーシャルサポートネットワーク構築支援
- 既存の疾病、被災により新たに発症した疾病の治療に関わるソーシャルワーク機能
- 発災前には顕在化していなかった生活上の問題が、被災により顕在化してくる問題へのソーシャルワーク機能
IV、防災としての避難行動要支援者支援とソーシャルワーク
災害被災者支援というと、すぐに発災直後の救命、救援が想定されるが、その支援のシステム化は当然大切であるが、それ以上に災害発災時の被害を少なくするために、事前の防災が重要になる。その一つが、「避難行動要支援者」への支援とソーシャルワークである。
#1
災害害対策基本法に基づき「避難行動要支援者」名簿の作成が全国の自治体に求められている。その内閣府の指針では、以下のような内容が求められている。
「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(内閣府、平成25(2013)年・平成8年「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の改訂)
- 「避難行動要支援者名簿」の作成----記載事項•住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由、その他市町村長が必要と認める事項
- 避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し名簿情報を提供することができる。本人の同意を得ることを要しない。
- 避難支援等関係者と連携した個別計画の策定
- 避難行動要支援者と避難支援者等関係者のマッチング
- 障害者団体等と連携したりするなどして、企画段階から避難行動要支援者の防災訓練への参加の機会を拡充することが適切である
#2
厚生労働省老健局振興課長、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長連名による「水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組について」(依頼)に基づく地域包括支援センター及び介護支援専門員等がハザートマップを理解し、利用者への周知に向けた取り組みを行うよう求めている。
#3
避難行動要支援者本人の同意を得た上で、かつプライバシー保護を十分踏まえた上で、各個人、各家庭の福祉避難所への避難経路、避難の際の支援の具体的内容、避難所における配慮すべき内容の把握(トイレ介助、歩行補助、服薬管理と確保の手配、授乳の場、アレルギー食品等々)等多岐に亘り大変ではあるが、その人、その家庭の実態把握をすることが重要である。
V、「DWAT」の訓練内容とソーシャルワーク支援との関係性----「DWAT」の派遣は応急期だけでいいのか
災害被災者支援としては72時間を目安とする救命救急医療支援体制としての「DMAT」が有名であるが、東日本大震災を契機に、被災者支援にはケアワークやソーシャルワークも必要ではないかということで「DWAT」が全国で設置されるようになってきている。
#1
「DWAT」の必要性、活動のあり方などは、2013年に厚生労働省の「セーフティネット支援対策等事業費補助金(社会福祉推進事業)」を活用して『災害福祉広域支援ネットワークの構築に向けての調査研究事業報告書』(委員長大橋謙策)と2018年3月に厚生労働省の「生活困窮者就労支援事業費等補助金(社会福祉推進事業)を活用して『災害時の福祉支援の在り方と標準化に関する調査研究事業報告書』(委員長大橋謙策)に詳しいので参照していただきたい。
#2
この「DWAT」の研修プログラムは現在必ずしも定式化されてはいない。
しかも、「DWAT」の派遣自体、緊急期、応急期を中心に考えられているので、中長期的支援ではコミュニティソーシャルワーク機能が求められている。
#3
先に述べた第2次報告書(2021年3月)においても、研修内容は派遣に関わるシステムや保健医療とのコーディネート機能、ロジスティックス機能等が中心で、避難所の運営についてとか、災害時の要配慮者支援の実際等の事例検討もされているが、直接的な対人援助におけるアセスメントの視点と枠組みとかナラティブを踏まえた被災者の求め、希望と専門職が必要と判断したことの両者を出し合ったうえでの支援方針の立案などのソーシャルケア(ケアワークとソーシャルワークとの有機化)に関する研修内容にはなっていない。
#4
日本の場合、被災者の中から、被災者の雇用対策もふくめて生活相談員が雇用され、被災者の安否確認なども含めて相談支援する生活相談員制度が活用されているが、これからは上記したようなソーシャルワーク支援が求められていることを被災者支援に入る人は事前に研修して、それなりの能力を身に付けておく必要がある。「DWAT」の派遣員自体が、被災者支援にはこのようなソーシャルワーク支援が求められていることを踏まえて支援に入るべきではないか。
石巻市では、被災後2年目から生活相談員制度とは異なる「地域福祉コーディネーター」を配置した。
V、被災者支援のソーシャルワーク
としては、
① 被災に伴う諸々の悲しみを受け止め、「生きる意欲」を引き出し、支えていく機能
② 長期的伴走支援機能
③ 専門多職種・機関のコーディネート機能
④ 人生再設計のフィナンシャルプランの作成支援機能
⑤ 行政手続きに関する代行機能及び同行支援機能
⑥ 一度破壊されたソーシャルサポートネットワークの再構築支援機能
⑦ 旧来のコミュニティの良さを活かした新しいコミュニティの形成支援
(参考文献)『東日本大震災被災者への10年間のソーシャルワーク実践』
監修 日本医療ソーシャルワーカー協会、大橋謙策編著、笹岡真弓、福井康江、西田知佳子、平野裕司
2.ケアリングコミュニティの形成と「社会福祉施設の地域貢献」
筆者は、1977年に大正大学で行われた日本社会福祉学会のシンポジストに指名され、学会デビューを果たした。その報告は、1978年の日本社会福祉学会紀要『社会福祉学』第19号に「施設の社会化と福祉実践ーー老人福祉施設を中心にー」として掲載されている。
筆者は、その論文において、社会福祉施設の社会化と地域化を進め、社会福祉施設を地域住民の生活を守る"共同利用施設"として位置づけるべきことを提言した。
その後、筆者は、2014年4月に『ケアとコミュニティ』(ミネルヴァ書房)を編者として上梓する。その本の中で「社会福祉におけるケアの思想とケアリングコミュニティの形成」と題する論文を書き、その一節で「ケアリングコミュニティの構築・コミュニティソーシャルワークの触媒機能」について言及した。
ケアリングコミュニティを構築するのには、地域の社会福祉施設が社会化、多機能化、地域化して、地域住民の生活を守る"共同利用施設"の役割を担うことの重要性を指摘した。
去る6月に行われた第38回日本地域福祉学会で「地域福祉優秀実践賞」を受賞した広島県福山市鞆の浦地区を基盤に実践を展開している「さくらホーム」の代表をしている羽田冨美江さん(理学療法士)が書かれた『超高齢社会の介護はおもしろい』(七七舎発行、CLC発売)を読んで、"我が意を得たり"と喜んだ。
まず、この本のサブタイトルが「介護職と住民でつくる地域共生のまち」というのが嬉しい。
第2には、筆者の1978年論文と同じに、「利用者さんを地域化する、「スタッフを地域化する」という理念を掲げて実践していることである。そのことにより、サービス利用者の居場所、生き甲斐が増進し、そのことを通して住民の意識が変わり、介護施設自体が地域の中に入り込んでいくというケアリングコミュニティづくりの実践が展開されている。
第3には、福山市鞆の浦地区といっても、人口3900人、高齢化率49・3%で、その地区の中がまた4地区に分かれていて、各地区の祭り、独自の文化を形成してきた地域状況を踏まえ、住民の自宅から半径400mの圏域ごとに小規模多機能型施設等を配置し、その施設が住民の生活を守る拠り所になっているという。これは、厚生労働省が進めている地域共生社会づくりの「小さな拠点」と同じ発想であり、事実上、それらの拠点施設が住民の生活を守る共同利用施設になっていて、ケアリングコミュニティを支えていることである。
第4には、「さくらホーム」で実践されているケア観が私の考え方と一致していることである。サービス利用者一人一人にあった、その人の生育歴や地域の人間関係、日常行動様式も十分踏まえたケアプランを作成提供していること、それを前提として、"介護とは相手の人生を支えることであり、生きる意欲をもち続けられようにサポートすること"であり、かつ"どんな人でも居場所がある地域とは、支援が必要な人を住民が自然に受け入れ、「相手に助けが必要なら、できる範囲で手を貸すのが当たり前」という文化がある町です"と言える羽田さんの生き方に大いなる共感をした。
皆さんには、是非、この本を読んで欲しい。そして同じような実践を全国で取り組みたいものである。
羽田さんの実践と同じように、ケアリングコミュニティづくりに取り組んでいる実践を書いた本を紹介するので、是非読んで頂きたい。
(参考文献)「ケアリングコミュニティの拠点としての施設・社会福祉法人の実践例」
- 『ソーシャルイノベーションー社会福祉法人佛子園が「ごちゃまぜ」で挑む地方再生』(監修 雄谷良成 ダイヤモンド社、2018年9月)
- 『里山人間主義の出番ですー福祉施設がポンプ役のまちづくり』指田志恵子著、あけび書房、2015年10月ーー社会福祉法人優輝会(広島県三次市)の実践)
(2024年7月24日記)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(「阪野貢 市民福祉教育研究所」で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。