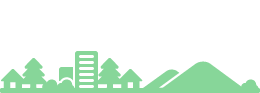老爺心お節介情報 第61号
本当に暑い夏ですね。
"夏の暑さにも負けず"、全国各地のCSW研修で飛び回っています。
7月13日~14日には、徳島県阿南市で第21回四国地域福祉実践研究セミナー(「こんぴらセミナー」から通算すると第27回になります)に参加してきました。600名もの参加者で、熱気溢れる、かつ実践報告の水準も高いセミナーでした。年々、参加市町村も増え、参加者も多彩となり、地域福祉研究者としては学びの多い、嬉しいセミナーでした。
恒例の句会も行われ、筆者も投句しました。選者は阿南市俳句協会の関係者で、覆面で審査してくれました。筆者の投句「時鳥、阿南の郷に人を呼び」がなんと特選3句の一つに選ばれました。
来年の第22回四国地域福祉実践研究セミナーは高知県黒潮町で行われることになりました。黒潮町は南海トラフで34mの津波が押し寄せると想定されている町です。「地域共生社会政策」で標榜されている多世代交流の「小さな拠点」のモデルとなっている高知県ふれあいあったかセンターを6か所も運営している町です(高知県全体で55か所)。黒潮町は重層的支援体制整備事業を受託しており、急速に、かつ着実に地域共生社会づくりが進展しています。
黒潮町は、「藁焼きカツオ」で有名な明神水産があり、セミナーへの参加と同時に、「藁焼きカツオ」とお酒での懇親会も楽しみです。来年、2025年7月12日~13日が開催予定日です。皆さん、大いに参加してください。
今回の「老爺心お節介情報」は、日本社会事業大学同窓会の北海道支部の機関紙『アガペ』に連載中の「虐待問題」のその④を転載します。『アガペ』への寄稿は、後一回でおしまいにしようと考えています。
筆者は、酷暑ではありますが、CSW研修で8月~9月も全国を飛び回っています。私のCSW研修は4日間か5日間のコースで、「社会生活モデル」に基づくアセスメント能力の向上、アウトリーチ型のロールプレイとその気づきの検証、地域住民が抱えているニーズに対応する問題解決プログラムの開発、地域での頃地を克服するソーシャルサポートネットワークづくりの課題を学ぶことを必須としています。前期課程と後期課程との間には宿題を出し、後期課程においてその宿題へのコンサルテーションを受講生一人一人に即して行うもので、かなりハードですし、公私の力量が問われるものです。改めて、地域福祉関係者、社会福祉協議会関係者の研修のあり方を問い直すべきではないでしょうか。
(2024年8月13日記)
<日本社会事業大学同窓会北海道支部・機関紙『アガぺ』寄稿その④>
(はじめに)
今まで3回に亘り、「虐待問題」が起きる根源的背景として、あるいは深層心理として持っている日本国民が有している文化的要因と社会福祉観、人間観について論述したうえで、ケア観の検討並びに画一的ケア観から個別支援におけるアセスメントの必要性について述べてきた。
今回は、それらを踏まえて、虐待の定義、現状について整理した上で、今後の「虐待問題」の検討すべき課題を提示した。
Ⅰ、虐待防止の法的定義と類型及び現状
虐待の問題は、子ども分野、障害者分野、高齢者分野において、共通する部分もあれば、異なる部分もあるので、虐待の法的定義とその類型及び状況については分野ごとに整理することとしたい。
① 高齢者分野における法的定義と虐待の類型及び現状
高齢者分野における虐待に関する法律は、2005年に制定された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という)がある。
その法律では、高齢者虐待の類型及び養護の定義を以下のように定めている。
ⅰ) 虐待の種類 身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、 経済的虐待
ⅱ) 高齢者とは65歳以上の者をいう
ⅲ) 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者をいう
ⅳ) 養介護施設従事者とは、介護保険法、老人福祉法等における業務に従事する者
高齢者虐待の状況は、厚生労働省が公表した令和4年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況などに関する調査結果」を基にした。ここでは、気になる項目を中心に抜粋しているので、詳しくはその調査を参照願いたい。
養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の推移の図表によれば、2022年度において相談件数は2795件(虐待と判断された件数は856件)で、前年度比16.9%の増となっている。「高齢者虐待防止法」が制定された翌年の通報件数が273件(虐待と判断された件数54件)であったことを考えるとその増加件数は約10倍で、高齢化率の増加を考えたとしても、かつ「高齢者虐待防止法」の周知度が高まったとしても大幅な伸びとなっている。
他方、養護者による虐待についてみると、2022年度の通報件数は38291件(虐待と判断された件数16669件)で、前年度比5.3%の増となっている。「高齢者虐待防止法」が制定された翌年の通報件数が18390件(虐待と判断された件数12569件)と比較しても増大している。
ただし、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約10倍なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約2倍(虐待と判断された件数では約1.3倍)なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見て取れる。
虐待が起きた養介護施設の種類別では、「特別養護老人ホーム」が最も多く、274件(32.0%)、次いで「有料老人ホーム」が221件(25.8%)、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」が102件(11.9%)、「介護老人保健施設」が90件(10.5%)となっている。
虐待の内容は、養介護施設従事者によるものでは、「身体的虐待」が810人(57.6%)、次いで「心理的虐待」が464人(33.0%)、「介護等放棄」が326人(23.2%)であった。
虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。
養護者による虐待では、虐待の発生要因(複数回答)としては「認知症の症状」が9430件(56.6%)、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が9038件(54.2%)、「理解力の不足や低下」が7983件(47.9%)、「知識や情報の不足」が7949件(47.7%)、「精神状態が安定していない」が7840件(47.0%)、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」が7748件(46.5%)であった。
養護者の虐待の内容(複数回答)は、「身体的虐待」が11167人(65.3%)、次いで「心理的虐待」が6660人(39.0%)、「介護等放棄」が3370人(19.7%)、「経済的虐待」が2540人(14.9%)であった。
被虐待高齢者の「認知症の程度」と「虐待種別」との関係では、被虐待高齢者に重度の認知症がある場合には「介護等放棄」、「経済的虐待」をうける割合が高く、軽度の認知症の場合には「身体的虐待」、「心理的虐待」が高い傾向がみられた。
② 障害者分野における法的定義と虐待の類型及び現状
障害者分野における虐待に関する法律は、2011年に制定された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という)がある。
と同時に、国連が制定した「障害者権利条約」(2008年発効)を日本政府が2014年に批准したことを受けて、2011年に障害者基本法が改正され、「障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止」が盛り込まれたことを受けて、その規定を具現化する「障害者差別解消法」が制定されていることも併行的に考えなければならない。
「障害者虐待防止法」では、障害者虐待の類型及び養護の定義を以下のように定めている。
ⅰ)「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
ⅱ)「障害者虐待」とは、ⅰ)養護者による障害者虐待、ⅱ)障害者福祉施設従事者 等による障害者虐待、ⅲ)使用者による障害者虐待をいう。
ⅲ)障害者虐待の類型は、ⅰ)身体的虐待、ⅱ)放棄・放置、ⅲ)心理的虐待、ⅳ)性的虐待、ⅴ)経済的虐待の5つとしている。
障害者虐待の現状については、2024年3月5日に行われた第140回の社会保障審議会障害者部会に報告された「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」に基づき明らかにしたい。
2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1300件増加している。「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の2012年度の相談・通報件数が3260件なので、約10年間で倍約2.6倍に増加している。
相談・通報件数のうち、虐待と判断された件数は2022年度で2123件で、これも2012年度に比べると1.6倍になっている。
相談・通報者は、警察が51%、本人13%、施設・事業所の職員が11%、相談支援専門員が11%である。
虐待行為の類型では、身体的虐待が69%、心理的虐待が32%、経済的虐待が17%、放棄・放置が11%、性的虐待が3%である。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待は、2022年度で4104件で、前年度より1.28倍増加している。そのうち、虐待判断件数は956件で、前年度比1.37倍である。
相談・通報者は、当該施設・事業所その他の職員が16%、設置者・管理者が15%、本人が16%、家族・親族が11%となっている。
虐待行為の類型は、身体的虐待52%、心理的虐待46%、性的虐待14%、放棄・放置が10%、経済的虐待が5%である。
被虐待者の障害種別では、知的障害が73%、身体障害が21%、精神障害が16%で、行動障害を伴うものでは34%になっている。
障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる"障害者を雇用している使用者"による虐待問題がある。
障害者虐待との通報・届け出があった事業所は、厚生労働省雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室の調査報告によれば、2021年度で1230件(都道府県からの報告197件、労働局などへの相談880件、その他労働局等の発見153件)であった。
通報・届出の対象となった障害者数は1431人であり、障害種別では、精神障害が37.8%、知的障害が32.3%、身体障害が19.1%、発達障害が7.1%となっている。
虐待行為の類型では、経済的虐待が47.5%、心理的虐待が37.8%、身体的虐待が8.3%、放置等による虐待が4.4%、性的虐待が1.9%となっている。
虐待の相談・通報があった件数のうち、虐待と認められた障害者数は、2021年度502人であった。
就労形態別では、パート等が46.4%、正社員32.9%、期間契約社員3.8%などとなっている。
障害者虐待を行った使用者の内訳では、事業主85.8%、所属の上司12.2%となっている。
虐待が認められた事業所の業種では、製造業25.5%、医療・福祉が22.7%、卸売業・小売業が11.2%、宿泊業・飲食サービス業が6.6%、建設業が5.9%となっている。
事業所の規模別では、5~29人規模の事業所が49.2%、30~49人規模が16.8%、5人未満が13.5%で、50~99人規模で6.9%、100~299人規模で3.8%となっている
③ 児童分野における法的定義と虐待の類型及び現状
児童分野における虐待に関する法律は、2000年に制定された「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という)がある。
児童分野における虐待については、1933年に「旧児童虐待防止法」が制定されていたが、これは戦後1947年に児童福祉法が制定されたことに伴い廃止されている。しかしながら、1990年代に入り、急速に児童虐待が増加したことに伴い、新しく「児童虐待防止法が」が制定されることになった。
「児童虐待防止法」では、児童の虐待の定義及び類型について以下のように定めている。
ⅰ)児童虐待の定義――「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人そ の他の者で、児童を現に監護するもの
ⅱ)児童虐待の類型――身体的虐待、性的虐待、保護者としての監護の放棄・放任、
心理的虐待
令和4年度(2022年度)中に、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は219170件でした。
筆者が日本社会事業大学の在外研究制度で、長期にイギリスに滞在したのは1992年であったが、当時イギリスの虐待件数は1990年当時約36000件だった。
しかしながら、イギリスの児童虐待の状況から考えて、日本でも家族形態の変容、地域における児童健全育成力の低下等から、急速に児童問題が深刻化し、児童虐待が増えると考え、筆者は全社協の全国民生児童委員協議会の企画委員会の委員長として、民生委員が児童委員を兼ねるだけでは対応できないと考えて、児童問題を主管、主務とする児童委員制度を創設すべきとの提案をした。その提案は厚生省に受け入れられ、1994年度から「主任児童委員制度」が始まる。
と同時に、筆者は東京都児童福祉審議会の専門部会長として、当時東京都にある12か所の児童相談所とは別に、各区市町村に最低1か所の「子ども家庭支援センター」を設置し、保健師、保育士、社会福祉士を配置して、子ども・家庭への相談支援を行うこと、しかもそれはアウトリーチ型の地域組織化を想定して行うことなどの提案をし、専門部会で承認され、東京都に建議した。その建議は受け入れられ、東京都全区市町村に58か所の「子ども家庭支援センター」が設置された。
この二つの提案は、イギリスでの在外研究制度の成果であり、日本でも急速に児童虐待への対応を図るべきとの提案であったが、当時の児童福祉研究者や児童福祉行政の関係者たちの反応は、従来の児童相談所体制でいいとする反応であった。
児童虐待は、筆者の想定した通り、1990年度には1101件で、その後2000年度には17725件、2010年度には56384件、2020年度では205044件と急増している。
2022年度の児童虐待の219170件の内容別件数は、「身体的虐待」が51679件(23.6%)、「ネグレクト」が35556件(16.2%)、「性的虐待」が2451件(1.1%)、「心理的虐待」が129484件(59.1%)となっている。
児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、2022年度では警察等が最も多く、112965件(51.5%)、次いで近隣・知人が24174件(11.0%)、家族・親戚が18436件(8.4%)、学校が14987件(6.8%)となっている。
児童虐待による死亡事件も2022年度では45件、51人が亡くなっている。子どもを巻き込んだ心中事件も37件、47人が亡くなっている。
虐待を行っている人の類型では、実母が38224件(57.3%)、実父が19311件(29.0%)、実父以外の父が4140件(6.2%)となっている。
虐待を受けた子どもの年齢別では、小学生が最も多く、23488件(35.2%)、次いで3歳~学齢前が16505件(24.7%)、0歳~3歳未満12503件(18.8%)、中学生9404件(14.1%)となっている。
児童分野における虐待発生の要因として、厚生労働省はⅰ)子どもの状況――発達・発育、健康状態・身体状況、情緒の安定性、問題行動、基本的な生活習慣、関係性、ⅱ)養育者の状況――健康状態等、性格的傾向、日常的世話の状況、養育能力等、子どもへの思い・態度、問題認識・問題対処能力、ⅲ)養育環境――夫婦・家族関係、家族形態の変化を挙げている。
Ⅱ、虐待の現状から抽出して論議すべき課題
このように「虐待問題」と一言で言っても、高齢者分野、障害者分野、児童分野といった多岐に亘っており、それを総括りして論議することは困難である。
強いて言えば、日本の「家」意識、画一的集団生活からの"逸脱者"への罰の意識、上意下達の命令体質がもたらす"複合的表出"の結果としての「虐待」と言えるのではないか。
とりわけ、日本の戦後の社会保障、社会福祉は、戦前の「家」制度の名残をとどめており、家族の扶養、家族の介護を家族間の情愛の感情、親密圏域の自然発生的ケア観を前提として構築されている。
社会福祉従事者もその呪縛から解放されておらず、家族を前提としたケア方針の立案をしがちであり、福祉サービス利用者を一個の独立した個人として捉え、その個人の幸福追求、自己実現を支援する役割を社会福祉関係者が担うという崇高な理念、人間像を描けないままに業務に従事していること、それらの職員を雇用する社会福祉法人などの組織自体も上記の理念を明確に持たないままの経営、運営に陥っているのではないかと思っている。
上記した虐待に現状について、今後検討する論議すべき課題との関係で、重要だと思われることを再掲しておきたい。
① 養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約10倍なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約2倍(虐待と判断された件数では約1.3倍)なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見て取れる。
② 虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。
③ 高齢者の養護者による虐待では、虐待の発生要因(複数回答)としては「認知症の症状」が9430件(56.6%)、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が9038件(54.2%)、「理解力の不足や低下」が7983件(47.9%)、「知識や情報の不足」が7949件(47.7%)、「精神状態が安定していない」が7840件(47.0%)、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」が7748件(46.5%)であった。
④ 2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1300件増加している。「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の2012年度の相談・通報件数が3260件なので、約10年間で倍約2.6倍に増加している。
⑤ 被虐待者の障害種別では、知的障害が73%、身体障害が21%、精神障害が16%で、行動障害を伴うものでは34%になっている。
⑥ 障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる"障害者を雇用している使用者"による虐待問題がある。
就労形態別では、パート等が46.4%、正社員32.9%、期間契約社員3.8%などとなっている。
事業所の規模別では、5~29人規模の事業所が49.2%、30~49人規模が16.8%、5人未満が13.5%で、50~99人規模で6.9%、100~299人規模で3.8%となっている
⑦ 児童虐待による死亡事件も2022年度では45件、51人が亡くなっている。子どもを巻き込んだ心中事件も37件、47人が亡くなっている。
虐待を行っている人の類型では、実母が38224件(57.3%)、実父が19311件(29.0%)、実父以外の父が4140件(6.2%)となっている。
日本では、いまだ「子どもの発見」が不十分で、子どもは親の付属物として捉え、子どもを親の意向に従わせる「命令と禁止」での子育てが払しょくできていない。
これらの「虐待の現状」から考えて、検討すべき課題は以下の通りである。
ⅰ)家族による親密圏域のケアを当たり前の前提として、公共圏域のケアの整備が十分でない問題。
この問題の中には、相談できる「福祉アクセシビリティ」の問題や介護支援専門員、障害者相談支援員のケア観の問題がある。
また、ケアをしている家族の社会福祉制度を活用する受援力、地域福祉サービス利用主体の形成が不十分の問題もある
ⅱ)養介護者が集積している社会福祉法人などのサービス供給組織の経営理念、運営方針等にケアのあり方、サービス利用者の尊厳の保持が具体的に明記され、それが常に研修等を通じて確認できているかどうかの問題ーー社会福祉現場に関わる動機、モチベーションとその内省、外化の機会の有無とアンガーマネジメントの研修
ⅲ)機関委任事務体制下では行政による措置施設職員の研修がおこなわれていたが、2000年以降は、社会福祉職員の研修は行政的には対応できておらず、個々のサービス供給組織により行われている。
しかも、メンター制度やOJTの機能はほとんどなく、入職後から独任官的に職務を任せられ、体系的な研修を通して、自らの実践を振り返り、検証する機会を持てていない。とりわけ小規模のサービス供給事業組織がそうである。
ⅳ)上記Ⅱ)の問題とも関わるが、従事者が安心してケアに従事できるかどうか、職場環境の整備との関係の問題と同時に、きちんとしたケア観を有している人を採用し、キャリアップについて見通しがもてる人事政策があるかどうかの問題
ⅴ)日常的に地域で障害者等とふれあい、その人の人格を尊重する機会である福祉教育の実践が地域、学校において行われているかの問題ーー人間の理解は頭での言語能力での理解だけでなく、福祉サービスを必要としている人の切り結びが重要
(2024年8月13日記)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。