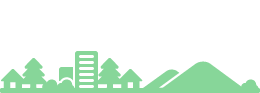老爺心お節介情報 第62号
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。私の方は、元気に各地の講演・研修で飛び回っています。
前回の「老爺心お節介情報」を出してから、だいぶ月日が経ちました。いろいろ伝えたいことはあったのですが、9月、10月と各地の講演・研修に忙殺され、書くことができませんでした。8~10月までの間で、これは伝えておいた方がいいと思うものをピックアップして送ります。
内容は、以下の通りです。
-
「我が青春譜」―東京都三鷹市勤労青年学級での10年間の学びと交流
-
前立腺がんの治療、処方が終わり、後は半年ごとの経過観察に移行
-
人口減少、超高齢化小規模町村の"地域"福祉は成り立つか?
-
敬愛する忍博次先生が逝去される
-
「我が青春譜」―東京都三鷹市勤労青年学級での10年間の学びと交流
去る8月31日に30回目の『きずな祭』が20名余の参加者を得て行われました。
『きずな祭』とは、故小川正美先生(三鷹市社会教育主事で、三鷹市勤労青年学級主事を兼ねていた)が1995年8月31日に亡くなられた翌年から、小川正美先生を偲び、その恩顧に報い、三鷹市勤労青年学級生同士の交流を深める目的で、小川先生の祥月命日の前後で行われてきた「祭り」です。
今回は、当時の勤労青年学級生もほぼ70代後半になっていることから、これが最後の『きずな祭』として行われました。
『きずな祭』は、小川正美先生の墓所のある八王子市犬目の明観寺での30回忌法要に参列し、お墓参りをしました。明観寺のご住職は、30回忌法要に青年学級生が20名近く参加したことを驚かれ、余ほど個人は人徳ある高邁な方だったのですねと法要の説話の中で述べられていたが、確かに葬儀ではなく、30年間も『きずな祭』が続いていること、30回忌の法要に子ども、親類を除いて、20名近くの当時の勤労青年が参列したことに感嘆されていた。
筆者は、故小川正美先生とは1965年からのお付き合いになる。小川正美先生は、東京学芸大学の社会教育主事養成課程において、私の恩師の故小川利夫先生と出会い、以後三多摩社会教育研究会のメンバーとして一緒に活動を行ってきた。故小川利夫先生曰く"義兄弟の契り"を結んだ仲であるという。
小川利夫先生は、日本社会事業大学の小川ゼミ、あるいは大学の講義科目である社会教育の科目をうけていた"貧乏学生"を三鷹市勤労青年学級に送り込み、勉強と同時にアルバイト先として活用していた。筆者も、日本社会事業大学学部4年の1966年から三鷹市勤労青年学級の講師補佐の役割を担い、社会教育の勉強の機会を与えられた。
筆者は、三鷹市勤労青年学級の社会コースの講師を1967年から勤め、日本社会事業大学の専任講師に採用された後の1975年までつとめさせて頂いた。
筆者にとって、中卒、高卒の勤労青年は社会教育と社会福祉の接点に存在する人々で、その学習者である青年の生活を垣間見ることにより、人間理解、生活分析、発達の可能性などについて考えることができたように思われる。
小川正美先生から、勤労青年学級の紀要ともいえる『青年学級の視点』に毎年のように教育実践のまとめと青年論についての原稿を書かされたのは苦痛であったが勉強になった。
三鷹市勤労青年学級の実践は、1960年代~1980年代に花開いた教育実践であるが、その実践は全国的にみても高く評価されていた教育実践である。その主な特色を箇条書き的に列挙すると以下のとおりである。
- 勤労青年学級の教育実践を各コース毎に毎年まとめ、『青年学級の視点』として刊行していた。その『青年学級の視点』には、青年教育論、勤労青年の生活分析などの小論文である拙稿も掲載されている。『青年学級の視点』に書かされたことにより、筆者はそれなりに書く"力"を身につけたように思える。
- 勤労青年学級の週刊新聞「きずな」を350号近くまで刊行したことである。これを発刊するために、学級生は「ガリ版」の筆耕を習い、発刊し続けた。この週刊新聞「きずな」の刊行が契機となり、三鷹市に独りぼっちの青年を無くそうという運動が、学級生から起こり、三鷹市の様々なところ(飲み屋、喫茶店なども含めて)に、学級生が作った「壁新聞」が張られることになる。
- 勤労青年学級は、毎年4コースほど開設されたが、講師は各分野の講師、あるいは大学院生が講師を務めていたが、講師補佐制度を作り、この講師補佐は学級生の中から選ばれ、学級運営について小川正美青年学級主事と話し合う機会をもっていた。講師補佐たちは合宿を行ったりして、自分たちの学級の運営や来年度に向けた企画立案を行った。
- 勤労青年学級生たちは、自分たちの居場所を確保するために、当時の三鷹市の市長である鈴木平三郎市長あてに手紙を書き、24時間自由になる居場所として公共施設を開放してもらい、その建物のカギを預からせてもらった。
- 勤労青年学級生は、三鷹市立図書館が使いづらいと考え、学級生の「みんなの文庫」を設立する。小学校で廃棄される下駄箱を譲り受け、洗い、ペンキを塗り、「みんなの文庫」として青年学級が行われている市民センターの一角に設置した。大学ノートを吊り下げておいて、借りていく人はそのノートに名前を書くだけの簡便な手続きにした。文庫の本はなくなるどころか増えていき、ある時にはLP版のレコードが多数寄贈されていた。
- 筆者が担当した「社会コース」では、ある年度、青年学級生の言語能力の向上、論理的思考法の獲得、大学生にコンプレックスを抱いている青年のコンプレックスからの解放といった教育理念の基に、三鷹市在住の絵本作家赤木由子著『はだかの天使』から読み始め、岩崎京子さんの童話『鯉のいる村』、あるいは青春ものを書いた早船ちよさんの『キューポラのある町』や早乙女勝元のものを読んだ。その後は、渡辺洋三さんの岩波新書『法とういうものの考え方』や美濃部亮吉の岩波新書『日本経済図説』なども読んだ。岩波新書を読むということは、大学生と同じくらいの学力があるのだと、コンプレックスをなくす一つの方法であった。この一連の読書の過程では、国語辞書の引き方等も学習し、知らないことが恥ずかしいことではない。学ぶ方法を身につけていないことが恥ずかしいのだと学級生たちと頑張ったことが強く印象に残っている。
- 三鷹市勤労青年学級には、重要な"たまり場"、"居場所"があった。それは学級が開かれている施設とは別に存在していた。それは今聡子さん(青森県出身)が経営していた「おでん屋」で、学級生からは「おばちゃんち」と呼ばれ、親しまれていた。そこが学級生たちの夕食の場であり、懇親の場であり、恋愛の場でもあった。勤労青年学級生たちが作成した『おばちゃんち』と題する記念誌も刊行されている。
この「おばちゃんち」で、酒を飲みながら、談論風発をしていたこともあって、小川正美先生が三鷹市教育委員会を退職するときには『酒会教育』という名の小川正美社会教育実践集が刊行されている。
筆者の地域福祉論における「地域福祉の4つの主体形成論」は、この三鷹市勤労青年学級の実践が基になるもので、筆者が各地で"住民座談会を行い、住民のニーズキャッチをし、それを基に行政への政策提言を行うという地域づくりの住民の主体形成論"として発展していく。
(2024年9月23日記)
2.前立腺がんの治療、処方が終わり、後は半年ごとの経過観察に移行
2022年3月に発見された前立腺がんは、2024年9月4日の診察で処方が終わり、服薬していた薬がなくなる9月末をもって治療が終了となった。
前立腺がんの腫瘍マーカーも、ここ1年0・008で推移しており、この数値は前立腺を除去しない限り0にはならないという。0・008は前立腺がんを治療できたと考えてよいとの医師の判断でした。
話には聞いていましたが、服薬していた女性ホルモン剤と女性ホルモン注射で、本当に筋力が落ちた。服薬が終わったので、筋力が戻りますかと医師に問うと、80歳代の人の筋力は20歳代の人の3分の1ですよ。戻らないと考えた方が賢明ですと言われたが、もう一度筋力を鍛えて歩きたいと考えることは夢想なのでしょうか?
(2024年9月29日記)
3.人口減少、超高齢化小規模町村の"地域"福祉は成り立つか?
以前にも「老爺心お節介情報」で取り上げましたが、人口減少、超高齢化した小規模町村や市町村合併に伴い社会福祉協議会が中央に集約化されて、合併後の「周辺地域」となった合併前の旧町村の地域力が急速に減退し、その地域の地域福祉が成り立たなくなってきている。
2023年6月の日本地域福祉学会の後に、長野市に合併した中条地区を訪ね、中条地区での"地域住民の自立生活"をどう支援するかということで懇談したが、2024年10月19日に改めて中条地区に入らせて頂いた。合併前の中条村は黒岩秀美さんをはじめとした社会福祉協議会が頑張って地域づくりをしていたが、合併後は長野市の"周辺地域"として、急速に地域力がぜい弱化していく。
長野市行政は総務省の「まちづくり協議会」の構想で対応しようとしているが、「まちづくり協議会」への補助金では専任職員を配置できない状況で、住民の負担が大きく、その地区はどうなっていくのかとても心配である。
今回の中条地区での住民との懇談は、古民家の囲炉裏を囲んでの「ろばた懇談会」でした。その「ろばた懇談会」では、従来の地域づくりが、ややもすると、いわゆる健常者住民中心の地域づくりに流れ、生活のしづらさを抱えている引きこもりの方や精神障害者の方々などを巻き込み、それらの人の社会参加促進とそれを支える地域づくりにはなってなかったのではないか、また具体的数字と其の人々がどこの集落に住んでいるかという臨場感ある具体的データに基づかずに"ともに生きましょう"という抽象論に終始していたのではないかという論議をさせて頂いた。
その翌日の10月20日には、長野県社会福祉協議会と長野県の未来基金とがジョイントしようとしている「小規模町村の活性化支援プロジェクト」の打ち合わせが小川村で行われるので参加した。
人口440人の売木村社会福祉協議会の圓口實局長、人口660人の王滝村社会福祉協議会の中嶋素道局長、人口1400人の小川村社会福祉協議会宮下隆男局長、築北市へ移住し、NPO法人わっこ谷の山福農林舎代表の和栗剛理事長を交えて、小規模町村の現状と支援のあり方について論議した。
これらの小規模町村からは、民間介護保険事業者が撤退し、社会福祉協議会の訪問介護によってかろうじて住民の生活支援ができていることなどが論議された。他方、合併により、かつ行政の集約化の中で、役場もなくなり、社会福祉協議会もなくなり、住民自身で地域を支えていく厳しさのある中条地区などの"周辺地域"の課題との比較を通して、今後の地域福祉のあり方について論議した。
来年の2月末には、長野県木曽郡の6町村における社会福祉協議会の経営と地域住民の自立生活支援を考える会合を持とうということを約束して帰路に就いた。
これに先立って、10月5日には島根県出雲市で「しまねの社会教育を振興する会」の主催で、以下のようなレジュメで講演をした。
島根県も440人の知夫村や雲南市の南部地域等小規模町村、人口減少、超高齢化地域の中で、地域住民は呻吟している。
島根での講演では、「社会教育と地域福祉の統合的実践のシステムづくり」が重要で、そのためにも地域住民自身が「選択的土着民」として筆者が作成した「ボランティア活動の構造図」のような取り組をしていくことが重要であると提言した。
「しまねの社会教育を振興する会」のレジュメなどは、阪野貢先生のブログ(ブログのフロントページ、「最近の記事」中の <まちづくりと市民福祉教育>(76))に収録されているので参照してください。ここでは、その一部を抜粋掲載しておきます。
『人口減少、超高齢化地域における自立生活を支援する社会教育と地域福祉の統合的実践――つながりの重要性と必要性』
(はじめに)
Ⅰ、戦後「第3の節目」としての地域共生社会政策
Ⅱ、地域共生社会政策の起点になった「新しい福祉提供ビジョン」(2015年9月)
Ⅲ、地域共生社会政策における包括的支援のあり方
Ⅳ、地域共生社会政策における重層的支援のあり方
Ⅴ、「地域福祉」の前提となる"地域"はあるかーー社会教育は地域づくりを忘れたか
# 地域福祉とは社会福祉の新しい考え方であり、新しいシステムをつくることであり、そのために住民の福祉意識を高める福祉教育の実践とコミュニティソーシャルワーク機能を発揮する実践をすること
③ 平成の市町村合併の功罪と地域福祉の衰退化――茅野市の実践、香川県さぬき市の経緯
④ 合併しなかった(できなかった)市町村と地域福祉実践及び「選択的土着民」の形成――秋田県藤里町、徳島県上勝町
⑤ 公民館活動を誇ってきた長野県・市町村の住民の選択と地域福祉実践
⑥ 『月刊社会教育』1984年6月号をめぐる論争――公民館の講座の高度化・体系化を図るのではなく、それらは大学開放、通信制の放送大学などに委ね、公民館は"実際生活に即する文化的教養を高める"地域づくりに回帰すべき――1990年「生涯学習振興法」制定
Ⅵ、社会教育と地域福祉の統合的実践のシステムづくり
① 公民館の戦前的源流(農村公会堂、隣保館、地方改良運動)と戦後初期の寺中構想に基づく公民館――自治型公民館 ――松江市出身の藤原英夫
② 1949年社会教育法の制定と公民館の変質及び市町村社会福祉協議会の組織化 ――牧賢一『社会福祉協議会読本』1953年――公民館が本来の機能を発揮しなくなってきているので、我々は市町村社会福祉協議会を設立するーー「社会福祉協議会から見た公民館」社会福祉協議会資料集第5集、1952年9月刊
③ 社会教育法第3条の"実際生活に即する文化的教養を高める"理念と青年団の「問題発見・問題解決型共同学習」
④ 4つの地域福祉の主体形成(地域福祉サービスの利用主体、地域福祉実践の主体形成、市町村地域 福祉計画の策定主体、社会保険契約の主体形成)と社会教育
⑤ 自立と連帯の社会・地域づくりにおけるボランティア活動の構造
⑥ 松江市公民館における公民館主事、保健師、社会福祉協議会職員の配置
Ⅶ、社会福祉施設の地域化と社会化
① 1971年「社会福祉施設緊急整備計画」による入所型社会福祉施設の時代
1978年論文・大橋謙策著「施設の社会化と福祉実践」(日本社会福祉学会紀要収録論文)――利用者の地域化、職員の地域化、社会福祉施設・資源の地域開放・地域利用、社会福祉法人としての地域貢献
「社会化」は、属性分野を超えた多機能化
② 「限界集落」、「消滅市町村」における地域力のぜい弱化の中で、"地域福祉"は成り立つのかーー地域住民の共同利用施設としての社会福祉施設の可能性―ケアリングコミュニティの形成
③ 施設経営の社会福祉法人の連携法人化と市町村社会福祉協議会の連携法人化――
権利擁護支援センターの広域化――一人暮らし高齢者・障害者の終末期支援・死後対応事務サービス
Ⅷ、新たな"地域"福祉の創造と社会福祉協議会及び社会教育の役割
① 障害者・高齢者のための「福祉のまちづくり」から、農福連携、社会福祉法人の経営における地産地消の「福祉でまちづくり」への発展と、今日における一人暮らし高齢者の移動、買い物支援、終末期・死後対応サービスを考えた「福祉はまちづくり」の時代
②自治会の力が弱くなり、各省推奨の「まちづくり協議会」の在り方と校区社会福祉協議会、住民会費を徴収している社会福祉協議会の位置――総務省「地域自治区制度」、総務省「地域運営組織」(一体型と分散型)
③ 一人暮らし高齢者、一人暮らし障害者の終末期支援及び死後対応サービスの整備――総務省が厚生労働省へこの件の整備の必要性の申し入れ
④民生児童委員との協働によるアウトリーチ型問題発見と個別課題ごとの問題解決プログラムを展開できる社会福祉協議会のみが"生き残れる"――香川県思いやりネットワーク事業、大阪府しあわせネットワーク事業
⑤社会福祉協議会の会費は「地域福祉共済保険」の掛け捨ての保険料――住民の生活上の事故(社会生活上のニーズ)に対応する支援、サービスの開発
⑥"実際生活に即する文化的教養を高める"社会教育の振興
(2024年10月27日記)
4.敬愛する忍博次先生が逝去される
日本地域福祉学会の名誉会員であり、北星学園大学の教授等をされた忍博次先生が、10月22日に逝去された。享年94歳であった。
筆者と忍博次先生との出会いは、日本地域福祉学会が設立される1987年以前の1982年である。
筆者が明治学院大学の三和治先生や日本女子大学の佐藤進先生、高橋誠一先生に依願されて日本社会事業学校連盟の事務局長に就任した時である。其の三和治先生が、国立身体障害者更生相談所(のちの国立身体障害者リハビリテーションセンター)で、忍博次先生と同僚であった関係で、いろいろ教えを乞う機会が増えていった。
忍博次先生とお酒を酌み交わした最後の機会は、2022年9月29日(当時92歳)に、札幌すすきので、大内高雄先生、白戸一秀先生、忍正人先生(忍博次先生のご子息)と懇親した機会である。
その日は、忍博次先生の北海道大学時代の恩師である城戸幡太郎先生、留岡清男先生(留岡幸助のご子息)、三井透先生などとの思い出話に花が咲いた。筆者自体は、留岡清男先生とは本(『教育農場50年』岩波書店)を通して存じ上げているだけで、三井透先生はお名前のみ知っている先生であった。
城戸幡太郎先生は、筆者の恩師である小川利夫先生と一粒社から『教育と福祉の理論』を出版するに際して、編集実務を担当していたこともあって、城戸幡太郎先生、官忠道先生、浦辺史先生、小川利夫先生の座談会(テーマは『「教育福祉」問題の現代的展望』)に陪席させて頂き、謦咳に接したことがある。座談会を終えて、小川利夫先生の命で、城戸幡太郎先生をご自宅までタクシーでお送りさせて頂いた(註2)。
そんなご縁もあり、忍博次先生と当時の北海道大学教育学部の恩師たちの話は大変参考になったし、もっと丁寧に聞き取りをしておくべきだったと後悔している。今となっては、"後悔先立たず"である。当時の北海道大学教育学部と東京大学教育学部は、憧れの教育学者が沢山いた。
亡くなられた忍博次先生は、気骨のある人で、かつ教条的ではなく、配慮できる先生であり、研究者とはこうあるべきという姿勢を我々に示してくださった。
忍博次先生は戦後の障害者研究、ノーマライゼーション研究を牽引された先生で、日本の社会福祉教育のあり方にも一家言を有している見識の高い、敬愛する先生であった。敬愛する先生がまた一人亡くなられた。淋しい限りである。
(註2)『教育と福祉の理論』(197.年刊、小川利夫・土井洋一編)の編集実務は筆者が一人で担ったが、出版に際し、恩師の小川利夫先生は、"大橋謙策は既に編著書があるので、編者に名前を入れず、土井洋一を共編者にして、大学の就職口を探してあげたいので、了承してほしい"と言われ、学問の世界はそんなものかと納得させられた。確かに、出版物の表紙に単著、共編著として名前が載るのは、研究者として、一つの評価のメルクマールであることは理解できる。
同じようなことは、筆者が日本社会教育学会の常任理事として、日本社会教育学会編集・刊行の『生活構造の変容と社会教育』(東洋館、1984年)の企画・編集を一手に担ったものの、出版に際し、当時の千野陽一学会長から伊藤三次先生の業績と大学との関係で、編集代表を伊藤三次先生にさせて欲しいと言われ、理不尽だと思いつつ了承させられたことがある。今のような研究倫理が厳しい状況であったら通らなかった事案である。
(2024年11月2日記)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。