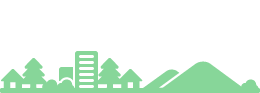老爺心お節介情報 第65号
< 梅の香で 頌寿を祝う 日和かな> 兼喬
立春を過ぎたというのに、余寒が厳しいこの頃です。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。
私の方は、2月はじめの金沢への出張先のホテルで、加湿器もつけず、マスクもせずに寝た結果、喉を痛め、風邪を引き、3週間近くすぐれませんでした。他方、正月明けに寝違えたのか、左腕の筋が痛く、時々筋に"電気が走る"といった痛さがあり、寝返りもままならない状況でしたが、漸く治り、ほぼ日常に戻りました。 (2025年2月22日記)
Ⅰ、人口減少・超過疎の超小規模町村の"地域"福祉を考える
2月19日、長野県木曽郡の郡内社会福祉協議会役職員研修に参加してきました。連日、気温が零下7℃、零下10℃の寒さの中、「過疎山間地域の福祉事業の未来について考える」がテーマでした。
四国の中で、一番面積が広い、かつ高齢化が進んでいる徳島県三好市地区で、日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞を受賞した社会福祉法人池田博愛が中心になって進めている社会福祉事業者連絡会は三好地区40事業所が参加をして、福祉人材確保や地域づくりに取り組んでいる実践ですが、当日はその実践を聞いた後、木曽郡内の社会福祉協議会、施設社会福祉法人が参加してシンポジュウムを行いました。
木曽郡内の人口は、王滝村が715人、上松町が4,131人、大桑村が3,439人、木曽町が10,584人、南木曽町が3,915人、木祖村が2,692人の郡内計で23,896人です(木曽郡の面積は香川県の面積と同じです。三好市は木曽郡内の人口規模とほぼ同じです)。
シンポジュウムには、長野県下伊那郡の売木村(人口548人)、泰阜村(人口1,542人)、天龍村(人口1,178人)や、南佐久郡の南相木村(人口962人)も参加され、さながら「超小規模町村の福祉サミット」の感がありました。
1990年代末から、町村社会福祉協議会は介護保険事業にシフトし、地域福祉の展開がおろそかになっていた状況の中での、人口減少、介護サービス利用者の減少、訪問介護報酬の減額化、福祉人材確保が困難となり、"社会福祉協議会はどう生き残れるのか"、"介護保険サービスは提供できるのか"、引いては"地域は消滅するのか"が大きな論議の中心でした。
詳しくは、長野県社会福祉協議会から報告書が出るでしょうから、とりあえずの一報はこの程度にとどめておきます。
3月26日には、長野県下伊那郡内の南信州を会場に、同じように「過疎山間地域の福祉事業の未来について考える」をテーマにシンポジュウムが開かれるとのことです。
長野県下伊那郡は、1966年の私が日本社会事業大学の3年時の春休み(当時21歳)に実習させて頂いた町村で、阿智村では岡庭一雄さん(永らく阿智村村長を歴任)宅に泊めて頂き、岡庭公民館主事、園原保健婦(当時)、生活普及改良員等の皆様と一緒に、地域講座に参加させて頂いた思い出の地域です。その実習が私のある意味、地域福祉実践の原点です。
その後、私は喬木村公民館で、当時の小渋川開発をどう受けとめるかという地域課題、松川町での第1回健康福祉祭りなどの事業に関わる実習を行いました。
3月26日には、30年振りぐらいの訪問になります。
Ⅱ、本の紹介―『社会的処方』(西智弘著、学芸出版社、2000円+税、2020年)
医療の世界では、長らくevidence of medicine が標ぼうされてきた。その医療の世界でも、最近では患者その人の生きざま、希望、物語を大事にするnarrative(物語)診療をうたう診療所も富山県南砺市や仙台市などで開業されてきている。
そのような中、social prescribing(社会的処方)という考え方が登場してきている。日本では、栃木県宇都宮市医師会に「社会的処方部」が開設されているし、岩手県釜石市でも「社会的処方」を推進している。
social prescribing(社会的処方)という考え方は、イギリスのNHSのプライマリケア領域で取り上げられ、2016年にはイギリスで全国的なネットワークが構築され、100以上の取組機関が加盟し、活動を展開しているという。
私は、1970年代に東京大学医学部の丸地先生等とプライマリケアの研究会をしていたが、その当時からWHOなどではこの考え方に関心を寄せていた。
千葉大学医学部の近藤克則先生(元日本福祉大学教授)たちも、"地域活動している人ほど認知症になりづらく、地域活動のリーダーほど認知症になっていない"という疫学調査を発表しているが、まさにその通りである。
高齢者には、"今日は要がある(教養)し、今日行くところがある(教育)"という"教養教育"が必要だと言っているのは、まさにその通りなのである。
『社会的処方』(西智弘著、学芸出版社)は、高齢者の孤独・孤立を防ぎ、認知症予防になるとともに、住民主体の地域づくりの重要性、必要性を実践的に述べている。
コミュニティデザイナーを標ぼうしている山崎亮さんも推薦している。