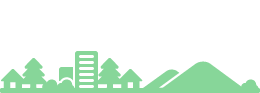老爺心お節介情報 第66号
皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。
先日嬉しい便りが舞い込んできました。韓国の金玄勲さんが、拙著『地域福祉とは何か』を翻訳してくれ、6月には出版記念会をソウル市で行いたいとの申し出でした。
『地域福祉とは何か』は、東北福祉大学大学院で教えた中国遼寧省の劉さんからも翻訳の意向が示され、現在進められています。
今「老爺心お節介情報」第66号は、虐待問題の連載の最終回です。この連載は、日本社会事業大学同窓会北海道支部の求めに応じて執筆連載してきました。とても重要で、かつ難しい問題でした。忌憚のないご意見を下さい。 (2025年3月2日記)
「社会福祉従事者の人間観、社会福祉観、生活観と虐待問題」その⑤・最終回
(はじめに)
虐待が起きている現場の状況は様々であり、その「違い」を捨象して、共通の統一的見解をしめすことは容易ではない。
しかも、今までも述べてきたように、日本人が有している国民的文化がもたらす人権感覚の低さ、多様性を認める認識の低さ等の、国民の深層心理、底流にある意識との関りを抜きにして語れない部分が多分にあるが、ここではそれを踏まえた上で、今後虐待問題を検討するに際しての課題について論述しておきた。
筆者は、連載の第4回の最後において、下記のような問題があることを指摘した。
それは、以下の通りである。最終会の今号では、これらについて論述したい。
ⅰ)家族による親密圏域のケアを当たり前の前提として、公共圏域のケアの整備が十分でない問題。
この問題の中には、相談できる「福祉アクセシビリティ」の問題や介護支援専門員、障害者相談支援員のケア観の問題がある。
また、ケアをしている家族の社会福祉制度を活用する受援力、地域福祉サービス利用主体の形成が不十分という問題もある
ⅱ)養介護者が集積している社会福祉法人などのサービス供給組織の経営理念、運営方針等においてケアのあり方、サービス利用者の尊厳の保持が具体的に明記され、それが常に研修等を通じて確認できているかどうかの問題ーー社会福祉現場に関わる動機、モチベーションとその内省、外化の機会の有無とアンガーマネジメントの研修
ⅲ)機関委任事務体制下では行政による措置施設職員の研修がおこなわれていたが、2000年以降は、社会福祉職員の研修は行政的には対応できておらず、個々のサービス供給組織により行われている。
しかも、メンター制度やOJTの機能はほとんどなく、入職後から独任官的に職務を任せられ、体系的な研修を通して、自らの実践を振り返り、検証する機会を持てていない。とりわけ小規模のサービス供給事業組織がそうである。
ⅳ)上記Ⅱ)の問題とも関わるが、従事者が安心してケアに従事できるかどうか、職場環境の整備との関係の問題と同時に、きちんとしたケア観を有している人を採用し、キャリアップについて見通しがもてる人事政策があるかどうかの問題
ⅴ)日常的に地域で障害者等とふれあい、その人の人格を尊重する機会である福祉教育の実践が地域、学校において行われているかの問題ー人間の理解は頭での言語能力での理解だけでなく、福祉サービスを必要としている人の切り結びを通して体感的に学ぶことが重要
Ⅰ、家族を"含み財産"とする社会福祉制度の破綻と「福祉アクセシビリティ」のいい「総合相談窓口」、「まるごと相談窓口」の設置及び福祉教育の推進
戦後日本の社会福祉制度は、家族を"含み財産"として位置づけ、家族の介護、養育を前提にして制度設計されてきた。
しかしながら、1960年代の高度経済成長政策の基、急速に産業構造の転換が行われ、
工業化、都市化、核家族化が進み、家族の、地域の介護力、養育力はぜい弱化していった。
そのことについては、拙稿「高度成長と地域福祉問題―地域福祉の主体形成と住民参加」(吉田久一編『社会福祉の形成と課題』1981年、所収)に論述してあるので参照して欲しい。
ところで、筆者が地域福祉と社会教育との学際的研究において、より明確に地方自治体における地域福祉とそれを可能ならしめる地域づくりを社会教育と地域福祉の有機的関りのもとで行おうと考えるようになったのは、江口英一先生が1968年に書いた「日本における社会保障の課題」という論文に触発されてからである。
社会教育はもともと地方分権を前提にして理論構築や実践が展開されていたが、社会福祉の分野における地方自治体の位置というものは必ずしも明確でなく、"福祉国家体制"という名のもとに、常に中央集権的機関委任事務の下で社会福祉行政は進められてきた。
社会保障の一環である社会保険は国レベルで検討される政策であることは理解できるが、社会保障の一環である対人援助としての社会福祉は地域で生活している住民の身近な地方自治体の政策として論議されるものだと筆者は考えてきた。
それは経済的給付とちがって、対人援助としての社会福祉は、地域性、地域の生活環境に左右される部分が多く、全国一律のサービス提供、対人援助にはなじまないと考えてきたからである。
江口英一先生は、先の論文で、地域住民の生活は大変不安定で、生活上のちょっとした事故でも住民の25%が生活保護世帯に転落する可能性を有していて、それを防ぐためには地方自治体ごとの福祉サービスの整備が必要であるとその論文で説かれていた。
筆者はこの論文に勇気づけられ、この論文に依拠しながら、どうしたら地域住民の生活を守り、安定させる福祉サービスの整備のあり方、提供のシステムができるかを考えてきたのが筆者の地域福祉研究60年であった。
その中の理論的、実践的課題の一つが「福祉アクセシビリティ」の問題である。それは住民の生活の安定を守る地方自治体の福祉サービスの整備量もさることながら、住民からみた「福祉アクセシビリティ」が大きな問題だと考えたからである。
「福祉アクセシビリティ」とは、距離的に近いという問題、公共交通機関の利便性、たらい回しをされない、ワンストップの相談の総合性、心理的、手続き面での受容性などが大きいと考えたからである。
1970年ごろ、国民の社会福祉認識は、社会福祉を利用する人、必要としている人は、ある意味で「自業自得」であり、福祉サービスを利用することは個人にとっても、家族・親類縁者にとっても"恥"とする意識が強かった。
このような福祉サービスを必要としていながら、福祉サービスの相談窓口が"縁遠かった"住民は、誰にも相談できず、ストレスを貯めこみ、ネグレクトするとか、心理的虐待、身体的虐待に走っていったことは想像に難くない。
住民の身近なところで、心理的負担もなく、相談しやすい環境があったならば、利用できる福祉サービスがある、なしに関わらず、住民は自ら抱える辛さ、悩み等を「外化」でき、虐待に走る度合いが減ったのではないだろうか。
今、地域共生社会政策の下で、包括的支援体制、重層的支援体制整備の必要性が謳われているが、1990年までの中央集権的機関委任事務体制の下では、「社会福祉六法体制」に基づく縦割り福祉行政がおこなわれていて、「福祉アクセシビリティ」のいい世帯・家族全体を支援する総合相談窓口はなかった。
筆者は1990年に東京都狛江市、東京都目黒区、岩手県遠野市などにおいて、縦割り福祉行政の弊害を除去し、住民にとって「福祉アクセシビリティ」のよい福祉行政システムを構築してきた。
このような「福祉アクセシビリティ」の良さに加えて、職員によるアウトリーチ型問題発見・支援とが行われたならば、養護者の虐待の動向は違っていたのではないだろうか。
日本の社会福祉・社会保障は、相も変わらず"家族の介護力、養育力"に依存する"家族"を含み財産とする発想が色濃く残っている。
今こそ、市町村において包括的・重層的支援システムを構築し、コミュニティソーシャルワーク機能を発揮できるシステムの構築とそれを担当できる職員の養成が喫緊の課題である。
今や、単身者社会であり、家族に頼らない、「福祉アクセシビリティ」のいい、生活に関わる「総合相談窓口や「まるごと相談窓口」を地域に構築することが必要である。
と同時に、住民の社会福祉に関する知識の向上、社会福祉制度の理解を深め、国民が戦前からの「家制度」に基づく「家意識」を変容させ、家族に頼らない、公共圏域の社会サービスを利用するのが当たり前と思える住民の福祉サービス利用の受援力を高める福祉教育の推進がますます重要になってきている。
Ⅱ、介護問題が集積している社会福祉法人の理念、経営方針と虐待問題
連載の第4回目で述べましたが、厚生労働省の調査によれば、障害者施設や通所サービスなどの従事者から障害者が虐待を受けた件数は、2023年度、5618件で前年度比約37%増加している(ちなみに、家族などの養護者から虐待を受けた障害者は2285件、前年比7・8%増であった)。
介護施設の職員らによる高齢者への虐待は1123件(前年度比31・2%増)で、2006年度調査開始以来の最多となった。家族などの養護者による虐待は17100件(前年度比2・6%増)であった。
このような状況を踏まえ、社会福祉施設、福祉サービス事業所での虐待をなくすためには以下のような取り組みが必要ではないか。
ⅰ)社会福祉法人の設立理念、経営方針における人間性、個人の尊厳を謳う個別ケアが明確化されているか
日本の社会福祉施設は、中央集権的機関委任事務が少なくとも1990年まで、あるいは2000年まで続いていたこともあり、福祉サービスを必要としている人、福祉サービスを利用している人のアセスメントが事実上できていなかった。
福祉サービスを必要としている人は、行政がサービス利用の要件に合致しているかどうかを判断し、社会福祉施設・社会福祉法人はその行政に措置された人を受け入れ、サービスを提供していたために、入所型施設などにおいては、三大介護と言われる食事、排せつ、入浴がどれだけ"自立"しているかというADLの評価が中心であった。
医療の世界では、ついこの間まで"やぶ医者"という言葉が住民の間で使われていたが、いまやその用語は"死語"になっている。それは、医療の世界では、聴診器だけでなく、レントゲン、MRI、CTスキャナー、血液検査などの診断技法が格段に進展し、患者の病変の診断と治療との関係性が格段に向上したからである。
ところが、社会福祉界は未だ福祉サービスを必要としている人が何につまずき、何が生活のしづらさを生み出す要因なのか、本人は何を希望し、どういう生活を送りたいと願っているのかなどの「社会生活モデル」に基づくアセスメント技法が確立していない。何となく社会福祉士、介護福祉士などの視角を有している人が"情感的に"判断しているという"やぶソーシャルワーカー"が沢山いる。
それは、福祉サービスを必要としている人が現に制度化されているサービスを利用できる要件に合致するかどうかという仕事の仕方をしてきた中央集権的機関委任事務体質の福祉文化を見直すことなく、無意識のうちにそれを引きずっているからである。
また、社会福祉法人は行政から措置された人に対する"最低限度の生活保障"をしてあげるという目線になりがちで、結果として法令による措置施設の施設最低基準に基づき集団的、画一的ケアを実施してきたのではないだろうか。
2000年以降、福祉サービス利用が契約で行われるようになった際に、従来の支援方針、ケア観を見直し、福祉サービスを必要としている人、利用している人と福祉サービスを提供側とが相対契約をする制度に変わってことに伴い、その際に、どれだけの社会福祉法人、社会福祉施設がその相対契約に相応しい福祉サービス利用者、福祉サービスを必要としている人の個々の状況に見合ったアセスメントと援助方針を確立することを明確にできたであろうか。
筆者が考えるのに、現象的には社会福祉法人も社会福祉も個人の尊厳、人間性の尊重を謡いながら、実質的には個々人の状況を丁寧にアセスメントするという福祉文化が確立できていないのではないか。
その点で、筆者が注目しているのは、2002年の老人福祉施設最低基準が改訂され、ユニットケアが出されてくる中で、一般社団法人日本ユニットケア推進センターが進めている限りなく個別ケアの具現化の取組である(拙編著『ユニットケアの哲学と実践』日本医療企画、2019年)。
一般社団法人日本ユニットケア推進センターが進めている個別ケアの実践は、同じ厚生労働省が定めた基準である老人福祉施設最低基準に則りながら、個別ケアが確立できており、かつ職員の離職率も低く、利用者からの評価も高いことを考えると全国的できないことではない。要は、社会福祉法人の経営理念、実践哲学がそのことを明かにできているかどうかの問題である。
ⅱ)市町村における福祉サービス事業所職員の研修の体系化はされているだろうか
中央集権的機関委任事務体制時代にあっては、行政がサービス提供を社会福祉法人に委託していたこともあって、各都道府県が社会福祉研修センターを設置し、社会福祉法人、社会福祉施設の職員に対する研修がそれなりに整えられていた。
しかしながら、2000年の介護保険、2005年の障害者総合支援法以降、福祉サービス利用は行政の措置から、福祉サービスを必要としている人と福祉サービス事業者との間の契約に変わったこともあり、各都道府県の社会福祉研修センターの役割は大きく変わり、
筆者が観る限りにおいて各都道府県の社会福祉職員に対する研修機能は大幅に低下していると言わざるを得ない。
ある意味、職員の研修は、各福祉サービス事業者の任意となり、行政は各サービス事業者のサービス管理者の資格、研修を規制化させることで、職員のサービスの質の担保を図る仕組みへと変更した。
したがって、福祉サービス事業で働く職員、社会福祉法人、社会福祉施設で働く職員の研修は、いわば無秩序状態になっている。
このような状況のなかで、小さな規模の事業所の職員はほとんど研修を受けることもできなければ、自前で研修をすると言うことも容易ではなくなってきている。先に挙げた事業所の虐待件数についても、事業所の規模や事業所内での研修の有無などについて丁寧に分析する必要があるが、ここでは触れない。ただし、福祉サービス事業所の規模別・虐待種別事業所数の調査によれば、規模が5~29人の規模の事業所が虐待件数全体の49.2%、30~49人規模が16.8%、5人未満が13.5%であり、逆に300人以上の規模では1.0%であることを考えると事業所の規模ごとにおける職員研修のあり方との関係があることは想像に難くない(「令和3年度使用者による障害者虐待の状況」調査)。
他方、1990年以降、地方分権化が進み、国や県は市町村への指導を直接的にはできず、専門的助言の域を超えることができなくなった。その上に、市町村は各分野ごとの福祉計画の"上位計画"として「地域福祉計画」を位置づけている。しかしながら、この市町村ごとの「地域福祉計画」を見る限り、市町村内の福祉サービスに従事する職員の研修の必要性を掲げている「地域福祉計画」は皆無に近い。
今や、一部の大手を除くと福祉サービス事業所、社会福祉法人の職員の研修システムはとても不十分だと言わざるを得ない。
しかしながら、福祉サービスは国民にとって欠かせないサービスであり、かつサービス利用費がいわば公定価格で縛られてはいるものの、逆の意味では"安定"していることもあり、いわゆる市場ベースの"競争原理"は働きにくい状況である。
ならば、サービス管理者の資格、研修のみならず、市町村福祉行政による市町村内の社会福祉職員の研修を整備し、職員の資質向上を図るべきなのではないだろうか。
2011年の「地方分権一括法」で、市域内だけの住民を対象に福祉サービスを提供している社会福祉法人の許認可権は市長が有することになったし、その後介護保険サービスの許認可権も市町村長に移譲されたことを考えると、市町村レベルでの域内の福祉サービス従事者への研修システムの構築は市町村行政が責任をもって行うべきではないだろうか。
このような職員の研修システムの構築をしないでおいて、事業所における虐待を取り締まるという姿勢だけでは問題解決につながらない。
ⅲ)社会福祉学の構造と国家資格養成課程における実践力習得の課題
社会福祉学の構造は、①社会福祉の目的、理念に関わる研究、②福祉サービスを必要としている人の生活のしづらさ、生活問題をアセスメントし、構造的に分析する分析科学、③福祉サービスを必要としている人の問題を解決するための援助方針の立案、活用できる福祉サービスの利用計画、活用できる福祉サービスがなければ、新しい問題解決プログラムと作成するとか、新しい福祉サービスを開発するなどの設計科学、④立案された援助方針、ケアプランに基づき具体的な対人援助の実践を展開する実践科学。この実践科学は、設計されたプラン通りに実施すればいいというものではなく、福祉サービスを必要としている人の日々の変化を見据え、実践者がその状況に合わせ、設計されたプラン、対人援助を微調整していく必要性がある。⑤実践を展開した後、福祉サービス利用者の「快・不快」を基底とした満足度や設計されたケアプランの妥当性などについての評価、振り返りを図る評価科学の5つの要素からなる統合科学である。
この統合科学という考え方は、戦前に確立されてき旧帝国大学の講座制の学問体系にはない、新しい学問の考え方であり、日本学術会議が2003年以降打ち出している考え方である。
社会福祉分野は、従来「学問」ではなく、「論」の域を出ていないと学術界では言われてきたが、日本学術会議の提案による「統合科学」という視点、枠組みを考えるならば、まさにぴったりの「統合科学」である。この「統合科学」という考え方の提唱もあって、社会福祉学は2003年度から日本学術振興会の科学研究費の細目として「社会福祉学」が位置づけられ、文字通り日本の学問体系において「社会福祉学」が認証された。
しかしながら、統合科学としての「社会福祉学」における個々の要因、要素の実践、研究の科学化は未だ道遠しの状況である。
第1には、援助方針を立てる基になるアセスメントが十分確立されていない。相も変わらず医学モデルに基づく"治療"、"療育"という考え方が強く、「社会生活モデル」に基づく、その人の自己実現を図るという発想が十分でない。そのことは先に述べた中央集権的機関委任事務体制の文化的名残りであり、かつ憲法第25条に基づく最低限度の生活保障を保証してあげるというパターナリズムを払しょくできていないからである。
今や、ICF(国際生活機能分類)の考え方に基づき、福祉機器等を活用してその人の生活環境を改善したらどうなるかという視点からのアセスメントも重要になってきている。
第2には、社会福祉の実践現場は、施設最低基準などの制約があり、ややもすると新人職員と言えども"一人前"の扱いを受けて、勤務シフトに配属され、事実上OJT―オン・ザ・ジョブ・トレーニング(職場での実務を通じて知識やスキルを習得させる育成方法)が実施されてない。
また、同じような理由から職員の資質を向上させる一つの方法であるメンター制度(経験豊富な先輩社員・メンターが後輩社員のキャリア形成や悩み解決法をサポートする社内制度)なども導入されていないのが大方である。
今日では、社会福祉士、介護福祉士の国家資格が出来てから約40年近くの歴史を経て、多くの社会福祉従事者が資格を有する時代になってきている。
先に述べた虐待事案において、国家資格の有資格者が虐待を起こしているのか、それとも資格を有していない人が虐待を起こしているのかの分析まではしきれていない(障害者分野では、虐待を起こした職員の就労形態別調査では、正社員、パート等において虐待がおこされていて、派遣労働者等の件数は少ない。しかしながら、国家資格の有無による虐待件数の調査は見当たらなかった。高齢者分野においてもこの項目は見当たらなかった)。
資格を有していない人が虐待問題を起こしていてもしょうがないという訳ではないが、資格を有している人でも虐待を起こしているかもしれないという問題点をここでは指摘しておきたい。
つまり、現在の国家資格は、社会福祉制度などに関わる座学で学べる部分と実習によって習得できる部分で教育課程は構成されているが、筆者は圧倒的に実習が少ないと考えている。
社会福祉士の国家資格の受験資格を得られる通信制の養成機関では、出題科目である講義科目についての履修は求められず、相談援助に関する演習と実習が課せられている。
この考え方は、講義科目は当然国家試験に出題されるので、その理解の程度を計ることは国家試験で行えばいいのであり、その国家試験をクリアできなければ合格できないので、それで一種のスクリーニングが行われているという考え方である。
しかしながら、相談援助に関する技術は演習で見に着けなければ習得できないので、必修にすると言う考え方だった。当時の厚生労働省の高官はそのことを明言していた。
そうだとすると、社会福祉系大学などの養成校の通学生の講義科目についても同じことがいえるので、もっと選択の幅を増やして、負担を軽減し、その分演習や実習によって、座学で得られない実践力の取得に努めるべきではないか。
同じようなことは、社会福祉職員研修においてもいえることで、知識の量を増やす、新しい知見を身に着けることを目的とした講義を聞くという承り研修はe-ラーニングでも行うことができるので、対面での研修は少なくし、その分事例に基づき、その事例で起きた現象がどのような要因から出されてきたのかをアセスメントし、其の問題を解決する援助方針を立て、どのようなサービス、どのような支援を行うべきかのケアプランを作成するアクティブラーニングを質・量ともに増やすことが必要ではないか。それを行わない限り、"知識はあるけれど、対応ができない"という状況はなくならないし、国家資格を有していても虐待事案を起こすことになる。
ただ、このような事例に基づきコンサルテーションを行える大学の教員がどれだけいるかが大きな問題である。
第3には、医学部の入試において面接が重要な位置と役割を担ってきていることが評価されている。
社会福祉系大学において、社会福祉従事者の個人的資質を問う受験生の面接を行って、ソーシャルワーカー、ケアワーカーとしての適性を弁えるという取り組みをしている大学がどれだけあるのだろうか。
日本社会事業大学でも、面接を実施して社会福祉従事者としての資質を見抜くという課題は大きな問題であった。かつては、受験生全員の面接が行われていたが、大学経営と受験生の増大という課題の前に面接は受験科目から姿を消した。今、思い起せば、対人に関わることは受験における面接が亡くなっただけでなく、新入生のオリエンテーションキャンプ、3年次進学時のインテグレーションキャンプといい、対人関係を培う行事はカリキュラムから姿を消している。ソーシャルワーク関係の教員がその重要性を指摘し、順守することができず、教員の負担軽減という名の下で姿を消している。このような状況で、学生はソーシャルワーク機能に必要な実践力を高めることができるのであろうか。
職員個人的資質の面で言えば、怒りやすい、すぐ切れるとか言った問題は、全体の問題でもあると同時に、すぐれて個人的資質の問題でもあるので、アンガーマネージメントの研修を受けるとか、コーチングを受ける機会を増やすとかして、職員本人の「外化」の機会や「内省」の機会を持つことも重要である。
ⅳ)社会福祉施設最低基準等の見直しと福祉機器を利活用した職員の負担軽減、利用者のQOLの向上
虐待の問題は、福祉サービス利用者に対するケアワーカーやソーシャルワーカーの配置基準が劣悪であるからとか、労働条件が悪いから起きるというという労働環境劣悪説を唱える人もいるが、事柄はそう単純なものではない。
しかしながら、十分な労働環境が保障されず、気持ちの余裕もなくなり、身体的にも疲労が蓄積されている時に、虐待が起きやすいことは想像するのに難くない。
虐待案件の調査でそのような視点での分析が今後必要になるのではないか。しかし、こではそれについては触れない。
虐待の問題と職員の労働環境の悪さとの直接的相関性をいうことは簡単にはできないが、先に述べたように「ユニットケア」で「個別ケア」を徹底している社会福祉施設ではサービス利用者も家族も大変評価していること、並びにその「ユニットケア」で働いている職員の離職率が全介護事業所や全国社会福祉施設経営者協議会に加盟している事業と比較して、離職率が特段に低い事を考えると、それは施設最低基準に問題があるというより、先述したような施設の経営方針等に由来していると考えるのが妥当であろう。
とはいうものの、施設最低基準が見直され、福祉サービス利用者の空間的生活環境の整備が整えられ、集団的、画一的ケアの提供ではなく、サービス利用者の生活リズムに合わせた支援が可能となるような施設最低基準の見直しは確かに今後必要であろう。
現在、厚生労働省は高齢者分野での介護ロボット、見守りセンサー等のICTや福祉機器を活用しての「介護労働生産性向上センター」を設置する政策を進めていると同時に、「LIFE」といった介護現場のデータ化によるケアの科学化を進めている。
他方、障害者分野でもICTを活用した「障害者ICTサポートセンター」を設置して、障害者本人の生活の利便性を高めると同時に、社会福祉職員の負担軽減を図っている。
これら福祉機器の利活用は、職員の負担軽減のみならず、利用者のQOLの向上にも連動している重要な取り組みである。
しかし、それ以上に重要なのは、介護ロボットの利活用もさることながら、介護現場に介護リフトを導入することである。人力による抱え上げをするのではなく、介護リフトを利活用することによって、福祉サービス利用者の不安感は軽減するし、職員の腰痛予防にもなる。結果的に利用者と職員との会話の時間も増えるということも考えると、施設最低基準の人員配置基準の見直しのみなら、従来の人力による介護をするという福祉文化を変えることが今最も重要に取り組み課題である。
(注記)
本連載は、日本社会事業大学同窓会北海道支部の求めに応じて執筆したものである。連載は、「老爺心お節介情報」第51号、第52号、第59号、第61号、第66号が初出である。