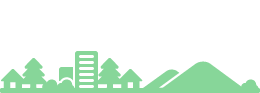老爺心お節介情報 第69号
皆さんお変わりありませんか。
春の季節はいいですね。我が家の庭では、ピンクと赤の牡丹が咲き誇っていましたが、それも終わり、今は、こでまり、シャガ、紫蘭が咲いています。シャガ、紫蘭はあまり魅力的な花だとは思っていなかったのですが、切って家に飾って、間近でよく見ると可憐な、とても魅力的な花だったことに今更ながら驚かされています。
我が家の庭の"猫の額"ほどの畑に、さやえんどう、シシトウ、キュウリ、ナス、トマトの苗を各4本づつ作付けしました。毎日、その成長を見るのが楽しみです。
毎年4月は各地の研修もなくのんびりしているのですが、今年は書斎の断捨離を始めました。2つあった書庫は既に断捨離をし、大方の本は東北福祉大学大学院の「大橋文庫」に寄贈しました。書斎にあった本は、自分の執筆に欠かせない本と断捨離をするのが忍び難い本が残っていました。その書斎の書棚に会った本をいよいよ断捨離することにしました。
自分の研究者としての人生が終わり、断筆しろと言われているようでとても辛い作業でしたが、思い切ってしました。書棚はガラガラで、残りは自分が書いた本が残っているだけです。
「老爺心お節介情報」第69号は、来る5月17日に行われる、石川県社会福祉協議会主催の「能登半島地震、集中豪雨の被災者支援から社会福祉関係者は何を学ぶか」のシンポジュウムのコーディネーターとして、社会福祉協議会が運営する新たな「災害福祉支援ネットワーク」がこれから考えておかなければならない「検討課題」(未定稿)について掲載しました。
もう一つは、6月28日から開催される日本地域福祉学会・武庫川女子大学大会において、上野谷加代子先生とトークセッションをする機会が与えられました。「次世代を担う地域福祉研究者、実践家に何を学び、何を継承して欲しいか」について話をしようと思っています。
二つとも未定稿で、これから関係者の意見を聞きながら推敲しますが、皆さんの興味、関心を呼び起こし、これらの集い、大会に参加して欲しいと思い、未定稿ながら「老爺心お節介情報」第69号を発刊、配信します。
(2025年4月29日記)
石川県社会福祉協議会主催
『能登半島地震・集中豪雨被災者支援から社会福祉関係者は何を学ぶか』
―災害被災者支援ソーシャルワークと外部支援受け入れのシステム・人材―
(シンポジュウムのねらい・目的)
東日本大震災等過去の震災において、社会福祉協議会関係者はじめ社会福祉関係者は多くの被災者支援、被災地支援をしてきました。
しかしながら、個々の組織、個々の団体の被災者支援の活動報告はあまたあるものの、社会福祉関係者全体の支援と課題を俯瞰的、鳥瞰的に討議し、整理したものは寡聞にしてしりません。
今回のシンポジュウム・中間報告会は、能登半島地震・集中豪雨被災者支援の全体を鳥瞰して、社会福祉関係者は何を学び、今後同じような不幸な災害が起きた時に対応するべきシステム、課題は何かを明らかにすることが目的です。
今回は社会福祉関係者が災害被災者支援において①日常的に取り組んでおくべきこと、②災害発災時に対応すべきことと、その運用システム、③外部からの被災者支援を受け入れるシステム、コーディネート、④とりわけ、ケアワーク、ソーシャルワークの支援を必要としている人々への支援のコーディネートと外部人材の確保、運用、⑤被災者支援に掛かる費用・財源の確保のあり方、⑤被災者支援に外部から入る個人、関係団体の調整、派遣のコーディネートと其のコーディネート人材確保のあり方などについて議論できればと思っています。
(具体的に検討したい事項)
- 福祉避難所の開設・運営のマネージメントー行政の危機管理課等との協働
- 一般避難所における要支援者のスクリーニングを誰が行い、その対応(福祉避難所への移動の必要性等)をどうするのか――障害を持つ人への配慮
- 避難所における食事、生活用品の確保、生活空間の確保、トイレの確保及び運営と外部支援の要請・受け入れのコーディネート及び運営のマネージメント
- 「避難行動要支援者名簿」登載者の安否確認をどういうシステムで行うのか、その人材
- 在宅福祉サービス利用者の安否確認と福祉サービス利用の状況確認――介護支援専門員・相談支援専門員等との協働
- 施設福祉サービス利用者の安否確認と福祉サービス利用の状況確認
- 福祉避難所、在宅福祉サービス利用者、仮設住宅等におけるケア及び生活支援としての「DWAT(災害福祉支援チーム)」の派遣の必要性把握と「DWAT」の受け入れのコーディネート及びマネージメント
- 入所型施設、グループホーム等におけるケア及び生活支援としての「DWAT(災害福祉支援チーム)」の派遣の必要性把握と「DWAT」の受け入れのコーディネート及びマネージメント
- 入所型施設などにおけるケアの提供が持続できるか、BCPの状況確認と対応策――社会福祉法人自体の責任、行政の責任、社会福祉協議会の責任
- 在宅福祉サービス提供事業者のBCPの状況確認と対応策――事業者自体の責任、行政の責任、社会福祉協議会の責任
- 被災者支援のために外部から入る支援者(DMAT、DWAT、各種専門職団体、各種NGO・NPO、技能ボランティア(団体・個人)、個人としてのボランティア等)の全体把握・受け入れ調整、活動調整のコーディネーターは誰が担うのか、またそのマネージメント
- 遠距離避難者・家族の把握と支援のマネージメントー避難先の社会福祉法人、社会福祉協議会に委ねるのか
- り災証明等の行政手続きの要支援者の確認と支援(同行手続き)
- 仮設住宅申請等の行政手続きの要支援者の確認と支援(同行手続き)
- 「みなし仮設住宅」住民の安否確認、生活支援の必要性把握と支援のマネージメント
- 仮設住宅等の入居被災者の安否確認・生活支援(新しい電気機器等の家具の使用法、買い物支援、郵便物の出し入れ、外部からの生活支援物資の配分、預貯金の出し入れ等)とコミュニティづくり
- 仮設住宅等の入居被災者及び在宅の被災者の心身ケアの必要性の把握と支援
- 既存の疾病、被災により新たに発症した疾病の治療に関わる支援
- 多世代家族の中で守られていた障害者(精神障害者、知的障害者等)が単身生活者になったことに伴う支援
- 復興住宅への入居や長期的生活再建への見通しとフィナンシャルプラン作成への支援(多くの被災高齢者は国民年金受給者で、被災前は農業、漁業等で自給自足的生活が可能であったが、被災後は現金収入がなく、預貯金も厳しい中での生活再建への復元力が弱い)
- 上記の災害被災者支援とそのコーディネートを行う法的根拠、権限、かかる費用の確保に掛かる課題と所管行政の窓口はどこで、社会福祉協議会との関りは?
- 被災者支援システムの平準化と重層的支援体制整備及びコミュニティソーシャルワーク機能を展開できるシステムづくり
日本地域福祉学会武庫川大学大会・トークセッション
『次世代を担う地域福祉研究者、実践家に何を学び、何を継承して欲しいのか』
(はじめに)
① なぜ、日本社会事業大学に進学したか?(『地域福祉研究』NO、42、「この人に聞く」聞き手上野谷加代子先生参照
② 地域福祉研究は日本社会事業大学でも、社会福祉学会でも「異端」扱い―阪野貢・市民福祉教育研究所電子書籍、大橋謙策アーカイブ・著書、第4巻『大橋謙策研究 第4巻 異端から正統へ・50年の闘い―「バッテリー型研究」方法の体系化―』市民福祉教育研究所/2025年2月1日/本編参照
Ⅰ.社会福祉研究者、とりわけ地域福祉研究者として何を研究的に明らかにしたいのか
① 自分が研究で取り上げたい社会生活問題と究めたい理論課題は何か
② どなたの学説を基に、それをどう乗り越えようとしているのか―先行研究批判
演者は、江口英一(貧困研究)、小川利夫(子どもの教育と福祉の学際研究)、岡村重夫(社会生活問題の主体的側面――ⅰ)奥田コミュニティ論と地方自治体論の欠如 ⅱ)地域コミュニティと福祉コミュニティの二元論の限界――福祉教育と主体形成 ⅲ)実践を担う職員論の欠如、
(『岡村理論の継承と展開 第1巻 社会福祉原論』ミネルヴァ書房、2012年)
Ⅱ.大学教員になるのが目的か、それとも何を学生に教授したいのか
① 教科書を教えるのか、教科書で教えるのか―教員、研究者として単著を書く意味
② 学生に教えるという視点ではなく、「学習者理解」を深め、演繹的に概念、制度を教えるのではなく、事例に基づいて帰納的に教えられているか
③ ビデオ、パワーポイントに頼っていないか、パワーポイントは"目で見る"ことにエネルギーを使い、講義を聴きながら"思いを巡らし"、何故かという疑問、質問を生み出す余裕ができない
Ⅲ.地域福祉実践・研究に求められる研究スタイルとはー「社会福祉学の性格と構造」
① 「統合科学」としての「社会福祉学の性格と構造」(図参照)を踏まえた研究
阪野貢・市民福祉教育研究所電子書籍、大橋謙策アーカイブ・著書、第4巻『大橋謙策研究 第4巻 異端から正統へ・50年の闘い―「バッテリー型研究」方法の体系化―』市民福祉教育研究所/2025年2月1日/本編参照
② 社会福祉教育に原論がなかった
ⅰ)原論、哲学を教えないで、社会福祉制度を教えることから日本社会事業大学の社会福祉教育は始まった―疑問、幻滅
③ その他の問題点
Ⅰ)社会福祉学会でも「社会福祉の目的、哲学」がなく、"広義の福祉と狭義の福祉"といった説明をしていた
ⅱ)社会福祉の目的である{自立生活}の捉え方が皆無であった
ⅲ)社会学との異同が意識されず、生活問題を分析することが社会福祉学であるとする風潮が強かった。にも拘わらず、その問題を分析、診断するアセスメントの視点・方法がなかった
ⅳ)問題解決をどのようなシステムでするのか、システムに関する研究(アドミニストレーション)が不十分
ⅴ)社会福祉方法論はあった(?)が、それを担う職員の養成、任用、研修の論議が十分でなかった
Ⅳ.地域福祉実践を・研究をどういう場所・機関で行おうとしているのか
① 演者は、主に市町村社会福祉協議会をフィールドにして、福祉教育、地域づくり(地区社会福祉協議会づくり)、新しい福祉サービスの開発をしてきた
② 都道府県(主に東京都、埼玉県、富山県)における各種委員会の委員として、積極的に新しいシステムづくりを提案
東京都児童審議会専門部会長として「子ども家庭支援センター」の設立、東京都生涯学習審議会会長として「地域教育プラットホーム」提言と具現化、東京都社会福祉審議会委員として「第3の分権化」の考え方とその必要性を提言、埼玉県社会福祉審議会会長として「新たな地域生活支援のあり方についてー共生・自立型社会福祉システムの構築―」(2008年9月)提言
③ 区市町村における委員会及び「地域福祉計画」策定において、在宅福祉サービス地区の設定、地域保健審議会の条例設置、保健と福祉の統合化による行政再編成を提言、具現化
Ⅴ.地域福祉実践・研究をどういう資質を持った職員と協働しようとしているのか
① 全社協「地域福祉活動指導員」養成課程に期待したこと―第1期からの講師
研修方法:開講された科目ごとのテキストを読んで、講師から出される課題へのレポートを提出、講師は添削して返却、科目履修修了者は1週間の集中合宿スクーリング
② コミュニティソーシャルワーク研修――4日間ないし5日間の研修、前期課程2日間、後期課程2日間、総括研修1日間
CSW研修では講義はほとんどなく、全てアクティブラーニング
ⅰ)複合問題を抱える家族を事例に取り上げ、「社会生活モデル」に基づくアセスメント(個人、グループ作業、全体コンサルテーション
ⅱ)取り上げた事例の支援方針作成
ⅲ)複合的な問題を抱えているヴァルネラビリティの人を想定したアウトリーチ型の訪問ロールプレイ(ビデオで収録してのコメント)
ⅳ)ロールプレイを演じての感想、気づきの記録化(宿題)とコンサルテーション
ⅴ)自らの業務上で対応したヴァルネラビリティの人の事例提出(宿題)とコンサルテーション
ⅵ)業務上、必要と感じている問題解決プログラム、新しい福祉サービスの開発(個人、グループ作業を踏まえて、最終的には個人として企画案の提出(宿題)とコンサルテーション
ⅶ)地域で孤立、孤独に陥っている人を想定して、その人の社会参加支援とソーシャルサポートネットワークづくり(個人とグループ作業を踏まえて、最終的に個人として企画案の提出(宿題)とコンサルテーション
③ 研修を受けた一定の資質を有した実践者の組織化と実践の「外化」を図る機会の創出
ⅰ)日本地域福祉学会の設立
ⅱ)日本地域福祉研究所の設立
ⅲ)日本地域福祉研究所の28回に亘る地域福祉実践研究セミナー、ⅳ)26回に亘る四国地域福祉実践研究セミナー
ⅴ)18回に亘る房総地域福祉実践研究セミナー
(参照)拙稿「地域福祉実践の神髄―福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク」阪野貢・市民福祉教育研究所「大橋謙策の福祉教育論」アーカイブ(2)論文所収
Ⅵ.地域福祉実践・研究における「バッテリー型研究」とは
① 研修、講師に呼ばれたからといって、その地域が自分のフィールドではない
② 「バッテリー型研究」におけるプロセスゴール(福祉教育、地域福祉の4つの主体形成)タスクゴール(新しい福祉サービスの開発、新しいシステムづくり)、リレーションシップゴール(地域福祉、社会福祉協議会を取り巻く環境の編アクト新しい力学の創出、「福祉はまちづくり」)
③ 研究者として、その地域の「関係人口」の一人として、継続的、専門的に助言、提言活動を展開できるか
富山県氷見市におけるアドバイザー業務(40年)、長野県茅野市におけるアドバイザー業務(15年)、東京都目黒区、豊島区、狛江市などにおける「地域福祉計画」づくりとその後計画に基づき設置した「地域保健福祉審議会」の会長としての計画の進行管理
(注記) 私の地域福祉研究、福祉教育研究などは、備考に書いてある阪野貢・市民福祉教育研究所の電子書籍にほぼ収録されているので、感心のある方はアクセスしてください。
参考文献
和田敏明著『和田敏明 地域福祉実践・研究のライフヒストリー』(香川県社会福祉協
議会発行、2024年3月 1500円)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。
阪野貢先生のブログには、「大橋謙策の福祉教育」というコーナーがあり、その「アーカイブ(1)・著書」の中に、阪野貢先生が編集された「大橋謙策の電子書籍」があります。
ご参照ください。
第1巻「四国お遍路紀行・熊野古道紀行―歩き来て自然と居きる意味を知るー」
第2巻「老爺心お節介情報―お変わりなくお過ごしでしょうかー」
第3巻「地域福祉と福祉教育―鼎談と講演―」
第4巻「異端から正統へ・50年の闘いー「バッテリー型研究」方法の体系化―」
第5巻「研修・講演録」
第6巻「経歴と研究業績」