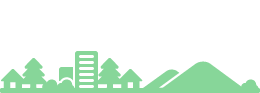老爺心お節介情報 第74号
酷暑は相変わらずですが、蜩やつくつく法師など、秋の気配をもたらすセミの鳴き声が聞こえるようになったと思ったら、それもすぐに聞こえなくなり、本当に異常な気候です。二十四節季の「処暑」を過ぎました。秋が待ち遠しいですね。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。
「老爺心お節介情報」第73号でお伝えしましたように、8月20日から22日まで、韓国の関係者に招聘され、ソウル特別市社会福祉協議会、韓国社会福祉協議会を訪問したり、「日本の地域福祉の碩学たちに"地域統合ケア"の路を問う」という韓日地域福祉学術講演会に参加してきました。
1990年代後半から2010年頃までは、毎年の如く韓国を訪問していたのですが、今回は久しぶりの学術交流の訪問でした。
今回の訪韓では、韓国社会福祉協議会会長金聖二先生(元韓国社会福祉学会会長、筆者が日本社会福祉学会会長の時、日韓学術交流協定した際の韓国学会の会長)、ソウル特別市社会福祉協議会会長金玄勲さん(日本社会事業大学の学部、大学院の教え子)、韓国在家老人福祉協会会長の趙南範さん(1997年の第1回の韓国地域福祉実践研究セミナーの際からの協力・支援者)、そして日本社会事業大学の大学院で博士の学位を取得した崔太子さん(韓国で在宅福祉サービス事業所を経営している会社の社長)をはじめ、多くの方々にお世話になりました。この紙上を借りて、改めて心よりお礼を申し上げます。
元国立光州大学の教授で、韓国社会福祉学会の会長をされた李英哲名誉教授も光州から駆けつけてくれましたし、私が日本社会事業大学の大学院研究科長をしている際に学位授与した厳基郁さんも国立群山大学総長になっていて、忙しいのに駆けつけてくれました。
日本からは、日本地域福祉研究所副理事長の田中英樹先生、日本福祉大学の原田正樹学長、全社協地域福祉推進委員会委員長の越智和子さん、文京学院大学の中島修先生、大正大学神山裕美先生、立命館大学呉世雄先生等総勢10名が参加しました。
2000年頃に日本で流行っていた「団子3兄弟」という歌がありましたが、それに倣って、かつて三浦文夫、愼ソプチョン(元韓国・国立釜山大学教授、元韓国社会福祉学会会長)、大橋謙策を旧「団子3兄弟」、大橋謙策、金聖二、李英哲を新「団子3兄弟」と呼んで、交流を深めていたものでしたが、その時の交流が思いだされ、旧交を温めることができ、とても感激しました。
韓国に到着した8月20日には、ロッテ・シティホテル・マッポで歓迎晩さん会を盛大に挙行してくれました。日本、韓国合わせて25名ほどの参加で、料理も美味しく、日本から持参した純米酒4合瓶、4本を楽しく空けながら、旧交を温めることが出来ました。
8月21日の午前中は、金玄勲さんが会長しているソウル特別市社会福祉協議会を表敬訪問しました。
今年で、6年目の会長職ということでしたが、着実にソウル市社会福祉協議会の活動を変容・発展させていることが実感できました。
第1番目に特記することは、民間企業等からの寄付者を増やしていることです。企業と一緒にイベントしたりして、日本では考えられないほど企業の社会貢献活動を引き出し、生活困窮者などの支援していることです。旧態依然の業務をしていた人たちは耐え切れず退職し、現在は殆どが1級社会福祉士の資格を有している新進気鋭の職員たちで構成されているとのことです。
第2番目は、職員たちと毎月1冊の本を読んで、論議をしていることです。職員の企画力、発言力が格段に成長したと言っていました。
第3番目には、企業などが寄付をしやすいように、今求められているニーズに合わせて問題解決プログラムを1冊にまとめ、それを持参してプログラム実現の寄付のお願いをしに、企業への売り込みを行っていることです。
日本の社会福祉協議会のように、行政からの補助金を期待するのではなく、自分たちが開発したプログラムをもって、企業に売り込みに行くという姿勢は素晴らしいことで、日本でも社会福祉協議会が学ばなければならない活動、姿勢だと思いました。
8月21日の午後は、ロッテ・シティホテル・マッポの近くのガーデンホテルで講演会が行われました。
当初、150名程度と考えていた参加者が200名を超える盛況で、部屋が埋め尽くされていました。
講演会には、韓国式の花輪が15基ほど寄せられ、会場を彩ってくれました。国立群山大学総長の厳基郁さんも花輪を出してくれていました。
講演会終了後には、拙著を翻訳した韓国版の『地域福祉とは何か』のサイン会をしてくれということで、汚い私の字ではと思いましたが、私が座右の銘にしている言葉を添えて40名ほどの方にサインをしました。
その後の懇親会は、まるで金玄勲さんの韓国社会福祉協議会会長選挙の"総決起集会"のような様相の懇親会になりました。
韓国社会福祉協議会の会長選挙は、各種社会福祉団体の全国組織、市町村社会福祉協議会の代表、会長から推薦・承認された個人会員、企業の代表からなる150名ほどが投票権を有しているとのことでした。11月末に、ある会場に集まり、直接投票するとのことで、日本の社会福祉協議会の会長選出とは全く異なる様相で、ある意味羨ましい光景です。韓国政治体制が大統領制なので、このような選出の仕方も韓国では当たり前なのでしょうが、日本人にとってはとても馴染みがありません。しかし、この方法も社会福祉協議会の活性化という点では日本も学ばなければならないかもしれません。日本でも、戦後初期に、公民館館長を直接選挙で選んだという歴史的実践がありました。
(2025年8月29日記)
<韓国・ソウルでの韓日交流学術講演会>
8月21日に行われた韓国・ソウルでの韓日交流学術講演会「日本の地域福祉の碩学たちに"地域統合ケア"の路を問う」では、日本側から筆者と原田正樹日本福祉大学学長が講演し、コメンテーターを韓国の車興奉先生(元韓国保健福祉部長官、韓国で長期療養保険制度を導入する際の委員長で、日本にも当時3か月滞在し、日韓比較研究をされた)と韓国の地域社会福祉学会の会長であった大邱大学名誉教授の朴泰英先生、日本側からは日本医療大学の田中英樹先生がされた。
筆者は、拙著『地域福祉とは何か』に基づき、日本での地域福祉実践・研究の系譜とその考え方、システムなどを中心に話をした。原田正樹先生は、現在推進されている「地域共生社会政策」の重層的支援体制整備事業について話をされた。
筆者の講演の内容は、以下に掲載したとおりである。7月の初めに講演のレジュメを作成して韓国へ送ったあと、日本の地域包括ケアの歴史、現状について知りたいという韓国側の要請を受けて、別途「参考資料」を作成した。したがって、当日の講演は、講演のレジュメと後日送った参考資料とをミックスしたかたちで講演することになった。そのレジュメの分量は多いので、ここでは割愛し、韓国で話をした当日の内容の柱建てを以下に掲載しておきたい。
講演では「老爺心お節介情報」第73号で紹介した韓国の現状との比較も交えて話をした。
Ⅰ.「地域福祉」の概念―理念、目的
地域福祉とは、住民の身近な基礎自治体である区市町村を基盤に、在宅福祉サービスを整備し、障害者、子ども、高齢者を属性分野に分けず、全世代対応型で、地域での自立生活(労働的・経済的自立、精神的・文化的自立、身体的・健康的自立、家政管理的・生活技術的自立、社会関係的・人間関係的自立、政治的・契約的自立)を支援するという目的を具現化することである。
地域での自立生活支援においては、地域住民のエネルギーがプラスにもマイナスにも働くので、地域のヴァルネラビリティのある人に対する差別、偏見、蔑視を取り除き、排除しがちになる地域住民の社会福祉意識改革への取り組み(福祉教育)とそれらヴァルネラビリティのある人々を包含し、支援するという個別支援を通して地域を変えていくという住民参画型の福祉コミュニティづくり、ケアリングコミュニティづくりである(「ボランティア活動の構造図」参照)。
Ⅱ.日本の社会福祉界における「異端」から「正統」へー「地域福祉」の歴史的位置
筆者の「地域福祉とは」何かは、日本でも「地域福祉」は永らく社会福祉学界、実践現場で"異端"、"亜流"扱いだったのが、今やそれが正統になり、国の政策の主流になっていること、また、日本では1990年まで実質的にソーシャルワーク機能を展開できておらず、漸く2000年代に入り、在宅福祉サービスが"主流化"する中で、ケアマネジメントを活用したソーシャルワーク機能が"認知"されるようになり、今ではコミュニティソーシャルワーク機能が政策的にも、実践的にも必須の要件になってきている。
- 属性分野ごとの「社会福祉六法体制」(生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法)下において、「地域福祉」は任意団体である市町村社会福祉協議会が行う「地域の福祉の向上」という意味で、戦争遺家族の支援、共同募金活動、身体障害者等の当事者団体のお世話、老人クラブのお世話等を行っていた時代で、「地域福祉」研究、実践は社会福祉学界では「異端」だった。
- 演者は、そのような状況の中、1960年代以降「地域福祉と社会教育の学際研究・実践」を「異端」扱いされながら、市町村社会福祉協議会、市町村の公民館、社会教育を基盤に展開してきた。その際、演者は市町村社会福祉協議会の職員や公民館・社会教育の職員と「バッテリー型研究」のスタイルを取って行ってきた。「バッテリー型研究」とは、その市町村ごとに違う地域社会生活課題を分析し、その解決のあり方、システムを市町村社会福祉協議会の職員や公民館・社会教育の職員に提示して、協働してその問題解決や解決に必要なシステムを開発してきた。その上で、必要なら住民参加で市町村の「地域福祉計画」を策定するということを行ってきた。
- 「地域福祉」実践・研究を取り巻く政策的環境が徐々に変わり、1984年には社会福祉事業法が改正され、市町村社会福祉協議会が法律上認知され、位置付けられた。また、1990年には、それまで社会福祉法制上位置づけがなかった在宅福祉サービスが法定化され、施設福祉サービスとは違う在宅福祉サービスの実 践・研究がしやすくなった。在宅福祉サービスは、2000年の介護保険法、2005年の障害者総合支援法により、政策的にも、実践・研究的にも社会福祉政策のメインストリーム(主流化、正当化)になっていく。と同時に、「ソーシャルワーク」機能の重要性が重要視されるようになってくる。
- 日本では、イギリスのベヴァリッジ報告(「社会保険及び関連サービスについて」)と日本国憲法第89条に基づき、戦後「福祉国家論」説がもてはやされ、社会保険も公衆衛生も対人援助の社会福祉もすべて国家が責任を取り、行うものとの考え方が強かったが、対人援助サービスとしての在宅福祉サービスが法定化されるに及んで、社会福祉は基本的に住民の身近な市町村が計画的に責任をもって行うべきという考え方が1990年の法律改正で明確になり、かつ介護保険制度の実施により、一層求められるようになった。
Ⅲ.「地域福祉」を具現化させる方法論としてのコミュニティソーシャルワーク
コミュニティソーシャルワークという用語と考え方は、イギリスで1982年に発表された「バークレイ報告」の中に登場する。その要旨は、住民とソーシャルワーカーとが協働して地方自治体の社会サービスを展開する方法である。
日本では、先に述べた1990年の「生活支援地域福祉事業(仮称)の基本的考え方について(中間報告)」(座長大橋謙策)においてはじめて厚生省の文書に登場する。
演者なりにコミュニティソーシャルワーク機能をまとめると以下の通りである。
ⅰ) 地域にある潜在化しているニーズ(生活のしづらさ、生活問題を抱えている福祉サービスを必要としている人々)を発見し、その人や家族とつながる。
ⅱ) それらサービスを必要としている人々の問題を解決するために、生活問題の調査・分析・診断(アセスメント)を行い、その人々の思い、願い、意見を尊重して、「求めと必要と合意」(サービスを必要とする本人の求め、願いと専門職が必要と考えることを出し合ってのインフォームドコンセント)に基づき、問題解決方策を立案する。
ⅲ) その解決方策に基づき、活用できる福祉サービスを結び付け、利用・実施するケアプラン(サービス利用計画)をつくるケアマネジメントを行う。
ⅳ) もし、問題解決に必要なサービスが不足している場合、あるいはサービスがない場合には、新しいサービスを開発するプログラムを作る。
ⅴ) その上で、制度的サービス(フォーマルサービス)と近隣住民が有している非制度的助け合い・支え合い活動(インフォーマルケアが十分ない時にはその活動の育成・活性化を図ることも含める)の両者を有機的に結び付け、両者の協働によって、福祉サービスを必要としている人々の地域での自立生活支援を支えるための継続的対人援助活動を展開する。
Ⅳ.「地域福祉」を展開するシステムと圏域の重層化、機能の重層化の必要性
「地域福祉」を展開するシステムは、厚生労働省により定式化された行政組織が示されているわけではない。今や、中央集権的行政ではなく、地方分権、地方主権行政の時代である。演者が、日本の各市町村で社会実証的に取り組んできたシステム、考え方は以下の通りであり、厚生労働省もほぼ同じ考え方で、現在重層的支援体制整備事業を進めている。
ⅰ)
「地域福祉」は、原則市町村を基盤に展開する。市町村は、住民参加の機関である「地域保健福祉審議会」を設置し、市町村の「地域福祉計画」を策定する。
ⅱ)
市町村といっても、住民の生活は交通の便、地形、商店等の生活圏域が異なる。まして、合併した市町村では地域社会生活課題は大きく異なる。
したがって、「地域福祉」を展開するに当たっては、市町村を第1層、第2層、第3層という具合に圏域を重層化させることが重要である。と同時に、各層で求められる機能も層毎に異なる。
「地域福祉」の展開には、「圏域の重層化」と「機能の重層化」がポイントである。
第1層は市町村圏域で、「地域保健福祉審議会」の運営や「地域福祉計画」づくり、全体の調整機能が求められる。
第2層は、一般的に在宅福祉サービス地区と呼ばれるもので、中学校区(人口2万弱)レベルが考えられる。日本の介護保険制度では、この中学校区レベルに地域包括支援センターを配置している。
演者は、在宅福祉サービス地区という考え方をデンマークの生活支援法、スウエーデンの社会サービスに学び、市町村を在宅福祉サービス地区に分けて、在宅福祉サービスの整備並びに提供するシステムを1980年代末に提唱する。
第2層には在宅福祉サービスに関わる専門職や施設福祉サービスを担っている専門職も多く存在しているので、個別支援における専門多機関、専門多職種連携などは第2層で展開される。
第2層では、属性分野ごとの相談窓口ではなく、全世代対応型の総合相談窓口を設置し、包括的相談体制を整備する必要がある。全国の中学校区ごとに設置されている地域包括支援センターが約5500か所あるので、ここが総合相談窓口になれば、住民の福祉アクセシビリティはとても良く機能する。
第3層は、一般的に小学校区レベル(人口約1万人)とし、福祉サービスを必要としている人を発見し、支える地域(層)である。
日本では、このレベルの地区(地域)に校区社会福祉協議会が設立されているし、この地区レベルに民生児童委員協議会が設定されている。一般的に住民の"地域"認識は、この小学校区レベルの地域をイメージしている。
この3層において、民生・児童委員や町内会、自治会の役員、校区社会福祉協議会の役員たちがインフォーマルケアを担ってくれている。したがって、コミュニティソーシャルワーク機能でいうフォーマルケアとインフォーマルケアとの両者の有機的協働は、この第3層で展開される。
第3層では、社会福祉協議会の職員などによるヴァルネラビリティのある人々に積極的にアウトリーチして発見、つながる活動が期待されている。
Ⅴ.「地域福祉」推進における住民参加及び住民の主体形成とインフォーマルケア
「地域福祉」とは、福祉サービスを必要としている人も含めて地域での自立生活支援を目的にするので、病院の入院患者や入所型施設の利用者とは異なり、日常面での多様な近隣関係が良好でないとうまくいかない。ゴミ出しの問題、安否確認、避難行動支援等行政の力だけでは対応できない。どうしても近隣住民の協力がなければできない。まして、工業化、都市化した状況の中では、農業生産を中心とした産業構造時代のように家族に頼ることはできない時代である。
そのような中、福祉サービスを必要としている人を支える住民なのか、排除、蔑視する住民なのかが問われる。
今、限界集落、人口減少、超高齢化社会の中で求められる住民像は、「地域に生れただけでなく、生まれた地域を愛し、共に地域を豊かにしようとボランティア精神旺盛な『選択的土着民』」の養成、形成である。
従来は、この機能に深く関わってきた行政は社会教育行政、公民館であった。現在では内閣府、総務省も「まちづくり協議会」の設置を提唱せざるを得ない状況である。
市町村社会福祉協議会は、福祉サービスを必要としている人への個別支援と同時に、それらの支援が地域で支えられるような地域づくりをすることも同時に求められている(「ボランティア活動の構造図」参照)
これら、地域における住民による支援を求めれば求めるほど、住民には権利としての行政への住民参加の権限を担保する必要がある。「地域保健福祉審議会」はその一例である。
Ⅵ. 地域包括(トータル)ケアシステムに関わる歴史的ベクトル
- 1994年設置の岩手県遠野市「健康福祉の里」(国保診療所併設)と県立遠野病院との連携システムによる地域福祉実践のベクトルー1993年遠野市ハートフルプラン策定
(『21世紀型トータルケアシステムの創造』2002年、万葉舎参照) - 2000年実施の長野県茅野市における保健・医療・福祉の複合型拠点及び日常生活圏域毎のシステムによる地域福祉実践からのベクトルー診療所を核とした通所型・訪問型サービスとインフォーマルケアとの有機化、病診連携を踏まえた診療所の併設をシステム化した保健福祉サービスセンターの創設
(『福祉21ビーナスプランの挑戦』中央法規、2003年参照) - 『地域包括ケア研究会ー2025年問題』(座長田中滋、2013年)の問題提起による政策ベクトルー在宅医療連携診療所、医療と介護の連続的改革
# 生活圏域でのケアの一体的提供とその社会資源(インフォーマルを含めて)整備を地域包括支援センターを中心に構築するーー ①持続的な介護サービスの充実と基盤整備、 ②介護と医療の連携強化、 ③サービス付き高齢者住宅の整備、 ④認知症ケアの体系的な推進、 ⑤介護人材の確保とキャリアアップシステムの構築、 ⑥地域における高齢者の孤立等への対応、 ⑦低所得高齢者への配慮ある展開等
Ⅶ. 地域包括支援センターのモデル――長野県茅野市における地域トータルケアシステムの拠点としての保健福祉サービスセンターの設置(『福祉21ビーナスプランの挑戦』中央法規、2003年参照)
- 茅野市福祉担当行政アドバイザーとして、地域福祉計画において提案・2000年より実施――人口5万7千人で、八ヶ岳山麓の広範囲の市域を4つの在宅福祉サービス地区(小学校区9地区、中学校区4地区、行政区10区)に分け、その各々に保健福祉サービスセンターを設置し、市役所内にいた福祉事務所の職員、保健課の保健師を再編成して配属。それに加えて市社会福祉協議会の職員も配属――1982年スウェーデン「社会サービス法」を参考。
- 保健福祉サービスセンターには、内科クリニック、高齢者デイサービス、訪問看護、訪問介護、地域交流センターを併設。内科クリニックと諏訪中央病院との病診連携、「かかりつけ医」制度の促進。サービス供給組織は、JAや社会福祉協議会等多様。
- 保健福祉サービスセンターは、子ども、障害者、高齢者の全世代に対応するワンストップサービスを展開。基本的には、行政職員(ソーシャルワーカー)、保健師、社会福祉協議会職員(ソーシャルワーカー)が3人1組でチームアプローチをする。設置1年後からは、保健福祉センターには社会福祉協議会職員を各1名増員。
- 各センターへ社会福祉協議会職員(ソーシャルワーカー)を配属したのは、地域住民の福祉教育の促進、アウトリーチ型問題発見、ニーズキャッチの向上、住民のインフォーマルケア力の向上と活用の促進を図るため(年間280日地域を訪問)。
Ⅷ. 社会生活モデルに基づく地域生活支援――医学モデル、入所モデルと違う
- 地域生活支援では家族が果たしてきた機能、入所型施設が提供してきた機能を地域において本人の求めと専門職が必要とした判断とを踏まえた両者の合意による支援方針の決定とケアマネジメント及びサービス提供が必要
- その際に必要なアセスメントは、入所型施設でのADLを重視したアセスメント、疾病・治療における医学モデルのアセスメントではなく、社会生活モデルに基づくアセスメントが求められる
(アセスメントの大項目===生い立ち、願い等のナラティブ、労働的・経済的自立、精神的・文化的自立、身体的・健康的自立、生活技術的・家政管理的自立、社会関係的・人間関係的自立、政治的・契約的自立、住居、ソーシャルサポートネットワーク)
#3 イギリスでは、2016年に社会的処方(SOCIAL PRESCRIBING)という考え方が、NHSのプライマリケア領域で提唱され、全国ネットワークが結成された
Ⅸ. 障害者・高齢者のための"福祉のまちづくり"から「福祉でまちづくり」及び「福祉はまちづくり」への転換
- 農業の第6次産業化のみならず、障農連携・農福連携、あるいは契約栽培に基づく施設経営社会福祉法人の地産・地消経済による農業の第8次化の振興
- 施設経営社会福祉法人の地域貢献と施設機能の社会化、地域化
Ⅹ. 地域住民の孤立化,ソーシャルサポートネットワークの脆弱化と触媒としてのコミュニティソーシャルワーク機能
- 1960年代末からの「新しい貧困」の登場と地域住民の孤立化,ソーシャルサポートネットワークの脆弱化
- 1970年頃の子ども・青年の発達の歪み(人間関係・社会関係の希薄化、成就感・達成感の喪失、生活技術能力の脆弱化、帰属意識・準拠意識の希薄化、自己表現能力の脆弱化)の指摘と「生きる力」
- 都市化、工業化における「家庭の孤立化」とショックアブソーバー機能の脆弱化
- 都市化による「遊び場」の喪失と家屋構造の変容に伴う「中間空間」(縁側・土間・上がり框)の喪失による社会関係の希薄化
- 「街づくり」、コミュニティデザインにおける交流機能、居場所づくりの"復活"
- 住民活動の触媒、社会開発の触媒(物質の安定、物質の活性化、新しい物質の創造機能)としてのコミュニティソーシャルワーク機能
Ⅺ. 地域包括ケアの考え方と地域共生社会への発展
① 地域包括ケアの要件
ⅰ) 個別ケアにおける医療・保健・介護・福祉の専門多職種連携による包括ケア
ⅱ) 多問題家族・複合家族への世帯単位支援の包括ケア
ⅲ) 制度化されたフォーマルケアと住民によるインフォーマルなソーシャルサポートネットワークとを有機化して、提供する包括ケア
ⅳ) 単身高齢者・単身障害者等への「最期まで看取る」地域社会生活支援の包括ケア
ⅴ) 福祉機器等の合理的・効率的ケアの提供による住民のQOL(生活の質)を高める包括ケア
Ⅻ. 地域自立生活支援におけるICFの視点でケアマネジメントを手段として活用したソ
ーシャルワークの展開
- 価値・目的、ナラティブ(本人の生育史、願い、思い)に照らしたアセスメントの視点と枠組みとICF――福祉用具の活用とフィティング及び自立支援計画の立案
- アマネジメントにおけるサービスを必要としている人(ヴァルネラビリティ、利用しようと考えている人)へのエンパワーメントアプローチ
- ソーシャルワークにおけるニーズ対応型新しいサービス開発機能とケアマネジメント
- ソーシャルワークにおえる社会改善、ソーシャルアクション機能とケアマネジメント
- ケアマネジメントにおけるサービスプランニングと直接的対人援助としての伴走型ソーシャルワーク実践
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。
阪野貢先生のブログには、「大橋謙策の福祉教育」というコーナーがあり、その「アーカイブ(1)・著書」の中に、阪野貢先生が編集された「大橋謙策の電子書籍」があります。
ご参照ください。
第1巻「四国お遍路紀行・熊野古道紀行―歩き来て自然と居きる意味を知るー」
第2巻「老爺心お節介情報―お変わりなくお過ごしでしょうかー」
第3巻「地域福祉と福祉教育―鼎談と講演―」
第4巻「異端から正統へ・50年の闘いー「バッテリー型研究」方法の体系化―」
第5巻「研修・講演録―地域福祉の過去から未来へ」
第6巻「経歴と研究業績―地域福祉実践・研究の系」
第7巻「福祉でまちづくりー支え合う地域福祉実践・「まちづくりと福祉教育」の嚆矢」
第8巻「大橋謙策若き日の論考―地域福祉論の「原点」を探る」
別巻 「地域包括ケア・介護・CSW・潮流と展望~理論と実践・他人の土俵に乗る~」
ブックレット「社会福祉従事者の社会福祉観と虐待問題」