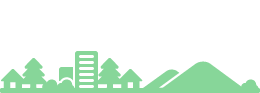理事長メッセージ
|
コロナ禍を超え、 特定非営利活動法人 日本地域福祉研究所 理事長 宮城 孝 |
 |
ご挨拶
2023年5月の総会を経て、前大橋謙策理事長の後を受けて、新たに理事長に就任致しました。またこの度、理事会・監事の役員も大幅に異動し、世代交代をすることとなりました。この点からも本研究所は、新たなスタートに立ったと言えるかと思います。大橋理事長を始め、長く本研究所の運営に協力していただいた皆様に心から感謝申し上げます。大橋先生には、引き続き顧問の立場から見守っていただきたくお願い申し上げます。
コロナ禍も3年を超え、ロシアによるウクライナ侵攻など国内外の環境は大きく変動しています。わが国は、超少子化、人口急減時代を迎え、その中にあって地域福祉は、既存の施策、実践、研究のあり様に安住していられない時代に入ったと思われます。例えば、国立社会保障・人口問題研究所が、2023年4月に公表した最新の「将来推計人口」では、2056年には総人口が1億人割れすると推定され、年間平均75万人の人口減少が予測されています。この人口急減、また、単身化、多死化など地域社会をめぐる社会環境は今後大きく変動していくことが予測されます。このような環境の変化に対してただとまどうだけでなく、これらの環境変化に伴うリスクを予測し、的確な目標を立て、中・長期的に効果的な施策と実践をたゆみなく継続していく営みが問われます。
全国の市町村自治体を概観すると、長期にわたる人口の流出や過疎化に悩みながら、自治体行政と地域住民が協働し、人口の流出や少子化に一定の歯止めをかけることができた地域があります。2019年に合計特殊出生率が2.95と驚くべき成果をあげた岡山県奈義町、また、日本一の子育て村を目指し、5年間の合計特殊出生率の平均で2.05を達成した島根県邑南町、その他島根県雲南市、島根県海士町、大分県豊後高田市、長野県宮田村、茨城県境町、千葉県流山市、兵庫県明石市などがあげられます。岡山県総社市、島根県出雲市などでは、外国人の転入増加により人口が社会増となっています。その他の自治体も含め、このような先進的な取り組みと成果をあげている自治体に共通しているのは、地域の将来への強い危機感の共有であり、首長の強いリーダーシップ、若い世代のニーズをきめ細かく把握した上での効果的・包括的な施策の実施、行政だけでなく、関係機関・地域住民と協働した取り組み、時間をかけた粘り強い継続的な取り組みなどがあげられます。
自らの目の前にある課題に真摯に向き合い、様々な関係者と協力関係を築きながら粘り強く挑戦していく。日本地域福祉研究所は、地域福祉の新たなステージに向けて、このような挑戦を皆様と共に広げていきたいと考えております。